UPDATE 2025.09.30
POST 2025.09.30
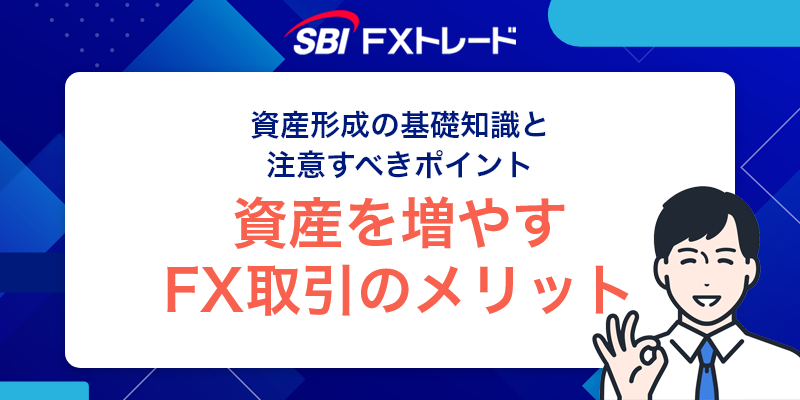
将来に備えてお金を増やす仕組みをつくる「資産形成」。政府が「貯蓄から投資へ」と呼びかけている背景もあり、年々取り組む方が増えています。
一方で、「自分も将来に備えて資産形成しておきたい」とは思うものの、何から始めればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そもそも資産形成とは何か、なぜ必要なのか、どんな手段があるのかといった資産形成の基礎知識を分かりやすく解説します。資産形成をする上で注意すべき点や、資産形成にFX(外国為替証拠金取引)が有効である理由などもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
資産形成とは、将来に向けて資産を増やすことや、その仕組みを築き上げていくことを意味します。
たとえば、毎月の収入の一部を貯蓄することで、老後や不測の事態に備える方法が挙げられます。
しかし、現代の低金利環境においては、それだけで十分な資産を築くことは難しく、インフレの影響でお金の価値が目減りする可能性もあります。そこで重要になるのが「資産運用」という考え方です。
資産運用とは、既に保有しているお金(資産)を、預貯金だけでなく、株式・債券・投資信託・不動産・FX(外国為替証拠金取引)などに配分し、効率よく増やしていく手法の総称です。
つまり、資産形成は労働収入や節約だけに頼るのではなく、時間と共にお金にも働いてもらうという発想で、将来の安心と経済的な余裕を確保するためにも、できるだけ早いうちから意識的に取り組むべき重要なテーマといえるでしょう。
資産形成を始める上で、まず重要になるのが「家計管理」と「ライフプランニング」です。生活にかかるお金を正確に把握し、将来に向けてどれだけ貯め、どう使うかを設計することが資産形成の土台になります。

家計管理とは、家庭生活において収入と支出のバランスをコントロールすることを指します。
毎月の支出を見える化し、無駄遣いを減らすことで、将来のライフプランや不測の出費にも備えやすくなります。
家計管理において特に重要なのが、収入から支出を差し引いた「黒字部分」を安定的に確保し、それを投資などの資産運用に回すという考え方です。このサイクルを継続することで、効率よく資産を増やせるため、将来的な安心感にもつながります。
ライフプランニングとは、人生における大きなイベントに備えて必要な資金を予測し、計画的に準備していくことです。
結婚・出産・住宅購入・子どもの進学・老後の生活など、人生にはまとまったお金が必要になる時期が何度も訪れます。自分の価値観や目標に応じて、どの時期にいくら必要かを見極め、無理のない資金計画を立てることが大切です。
一般的にライフプランニングは、教育・住宅・老後の「人生の三大資金」を柱に考えます。

教育資金とは、子どもの教育にかかる費用の総称です。
幼稚園から大学まで進学するのか、公立と私立のどちらを選択するのかなどによって費用は大きく異なり、選択した内容次第で子ども一人あたり2,000万円を超えるケースもあります。特に大学進学時は、入学金・授業料に加えて、仕送りや一人暮らしの生活費も想定しておく必要があるでしょう。
子どもの将来の選択肢を広げるためにも、できるだけ早い段階から教育費を見据えた準備を進めることが重要です。
住宅資金とは、住まいにかかる費用全般を指します。
持ち家の場合は、住宅の購入費用の他、ローンの返済や固定資産税、メンテナンス費用なども発生します。マンションの場合は、修繕積立金や管理費なども想定しておく必要があるでしょう。一方で、賃貸住宅は毎月の家賃や更新料などが継続的に発生します。
自分のライフスタイルや将来設計に応じて、どのような住まいを選ぶかを早めに検討し、必要な資金を計画的に準備しておくことが大切です。
老後資金とは、定年退職後に必要となる生活費や医療費などをまかなうための資金です。
多くの場合、退職後の主な収入源は年金になりますが、現状では年金だけで生活するのは難しいとされています。長寿化が進む中、老後が30年以上続く可能性もあり、生活費・介護費用・趣味・旅行などの支出も想定しておく必要があります。
今から先々のことを考えて、現役のうちから計画的に資金を積み立て、老後に向けた準備を進めておくことが大切です。
なぜ今、資産形成や資産運用が必要とされるのでしょうか。その背景には、低金利やインフレ、年金不安など、将来の生活に直結する課題が潜んでいます。
ここからは、資産形成・資産運用の必要性を3つの観点で解説します。
資産形成の第一歩として貯蓄は基本となりますが、貯蓄だけに頼るのはリスクがあります。
その大きな理由の一つが、現在の日本が長年続く低金利環境にあることです。過去においては、預貯金だけでもある程度の利息が期待できる時代もありましたが、現在では普通預金の金利は決して高いとはいえず、利息による増加はほとんど期待できません。それどころか、いくら預貯金に励んでも資産が増えずに、むしろインフレの影響によって実質的な価値が目減りする可能性すらあります。
もちろん、現金と預貯金は生活防衛資金として必要不可欠ですが、それだけでは将来の蓄えとして十分ではないため、中長期的に資産を増やしていくには、投資などの資産運用を組み合わせる必要が出てきます。
安全性と成長性のバランスを意識しながら、リスクを適切に管理し、計画的な資産形成を行うことが今後ますます求められています。

インフレとは、物やサービスの価格が全体的に上昇していく経済現象を指します。
緩やかなインフレは経済が成長している現れでもありますが、インフレが進むと現金や預貯金の実質的な価値が下がってしまう点には注意が必要です。例えば、今まで100円で買えていた商品が120円になれば、同じ100円でも買える物の量が減るため、相対的にお金の価値が目減りしたことになります。
そのため、利息がほとんどつかない低金利下で単に現金を銀行に預けているだけでは、インフレの進行によって実質的に資産が減っているのと同じ状態になります。
現在の日本では、光熱費や食料品、日用品などの値上げが続いており、実質的な家計の負担は確実に増しています。こうした状況に対応するためには、インフレに対して相対的に強い資産を選び、資産全体の実質的な価値を守ることが求められます。
資産形成・資産運用の手段だけでなく、インフレに強い資産は何かなどを理解し、自分なりの対策を講じていくことが求められています。
日本は少子高齢化に歯止めがかからず、将来の年金制度に対する不安がますます高まっています。
日本の年金制度は「賦課方式」となっていて、現役世代が支払う保険料で高齢者(年金受給者)の年金給付をまかなっています。少子化がさらに進行すると、公的年金の支給開始年齢の引き上げや年金給付水準の引き下げなどが予想され、年金制度そのものの信頼性が揺らぐ事態となってしまいます。
また、かつては終身雇用や年功序列に守られ、老後は退職金で安心して暮らせると考えられていましたが、近年は企業による退職金制度の縮小や、非正規雇用の増加により、会社員であっても将来の生活が保証されるとは限らなくなってきました。
医療費・介護費・住宅費の他、人生をより充実させるための趣味や旅行など、老後にもさまざまな費用がかかります。老後を豊かに安心して過ごすためには、現役時代からの計画的な資産形成や資産運用が欠かせません。
このような背景から、将来の自分を支える手段として、積極的に資産形成・資産運用に取り組むことが求められています。
資産形成では、やみくもに運用を始めるのではなく、自分に合ったリスクの取り方や投資スタンスを見極めることが大切です。ここからは、資産形成で特に意識すべき重要な注意点を解説します。
資産形成を進める上で欠かせないのが、リスクとリターンの関係を正しく理解することです。
リスクとリターンは基本的に比例関係にあり、リスクを低く抑えればリターンも小さくなり、逆に高いリターンを目指せばリスクも大きくなります。このバランスを理解せずに投資を行うと、思わぬ失敗につながる可能性があります。
また、リスクという言葉は「損失をこうむること」と誤解されがちですが、本来は「結果が不確実であること」を意味します。リスク自体は必ずしも悪いものではなく、投資の世界では不確実性は常にあるものと想定して行動します。
つまり、リスクは回避するというよりも、自分が許容できる範囲を見極め、コントロールして付き合っていく対象なのです。リスクに対してこのような認識を持つことで、無理のない投資判断ができるようになり、長期的な資産形成にもつながっていきます。

資産形成においては、自分がどれだけのリスクを受け入れられるかという「リスク許容度」を意識することが重要です。リスク許容度とは、どの程度までの損失であれば精神的・経済的に耐えられるかという度合いを示します。
リスク許容度は人によって異なり、以下のような要素によって左右されます。
【年齢】
若い方ほど運用期間が長く、損失を取り戻す時間があるためリスク許容度は高くなります。
【年収・資産の額】
収入や保有資産が多い方は、運用による損失をカバーしやすく、相対的にリスクを取る余裕があります。
【家族構成】
独身や扶養家族のいない方は、損失が家計に与える影響が少なく、リスク許容度が高くなる傾向にあり、家庭を持つ方はより慎重にならざるを得ません。
【投資経験】
運用経験が豊富で市場の値動きに慣れている方は、多少の損失にも冷静に対応できるため、許容度は高くなります。
【性格】
損失に対して過度に敏感な方はリスク許容度が低く、安定志向の運用スタイルが合う場合もあります。
このように、リスク許容度は年齢や環境、性格などによって変化します。自分に合った投資スタイルを見極め、無理のない資産配分を心がけることが資産形成成功の鍵となります。
資産形成においては、リスクの分散が重要です。
投資の格言に「卵は一つのかごに盛るな」というものがありますが、これは一つの投資先に集中すると損失が大きくなる可能性があるためです。リスクを分散すれば、一部の損失を他で補い、全体の資産を安定させることができます。
代表的なリスク分散の方法として「資産」「地域」「時間」の3つがあります。
資産の分散とは、異なる種類の金融商品を組み合わせて投資することを指します。
株式・債券・投資信託・不動産・現金などをバランスよく保有することで、一つの資産が減っても他でカバーしやすいため、全体のリスクを抑えることができるのです。
この考え方は「アセットアロケーション」や「ポートフォリオ戦略」とも呼ばれ、長期的な資産形成を目指す上で非常に有効な手法です。
地域の分散とは、複数の国や地域に投資先を分けることを指します。
例えば、日本だけでなく、米国・欧州・新興国など、異なる経済圏に分散投資を行うことで、一つの国の景気後退や政治的リスクが資産全体に与える影響を抑えられます。
経済成長のステージや通貨の値動きなどは地域によって大きく異なるため、それぞれを組み合わせて、より安定したポートフォリオを実現できます。
時間の分散とは、投資するタイミングを複数に分けて、リスクを抑えるという考え方です。
一度にまとめて投資すると、その直後に価格が下がると資産全体が下落するリスクがありますが、一定の間隔で定期的に購入すると取得価格の平準化が図れます。
この方法は「ドル・コスト平均法」という名称で知られており、比較的相場の変動が激しい場合や変化のスピードが早い場面で有効です。
一定の間隔で長期的に積み立てる方法は、感情に左右されず冷静な資産形成が可能になるため、初心者にも適した方法といえます。
資産形成にはさまざまな方法があり、それぞれ特徴やリスク・リターンが違います。ここからは、資産形成の代表的な8つの方法とその概要を解説します。
預貯金とは、銀行やゆうちょ銀行などの金融機関にお金を預け入れて利息を得る、資産形成の基本ともいえる方法です。
銀行などに預け入れる場合は「預金」、ゆうちょ銀行・JAバンクなどの場合は「貯金」と呼ばれており、他の手法に比べて比較的安全性が高く、普通預金であればいつでも引き出せる流動性の高さがメリットです。さらに、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度(ペイオフ)で保護される安全性が大きな特徴です。
ただし、現在の日本は超低金利時代にあり、利息による増加はそこまで期待できません。そのため、インフレが進行すると金額は増えていても実質的には資産価値が目減りする可能性があります。
預貯金は安全資産として活用しつつ、将来に備えて他の資産運用との併用を検討すべきでしょう。

株式とは、企業が事業拡大などの資金調達を目的に発行する有価証券です。
株式投資の最大の魅力は、企業の成長による株価の上昇から得られる「キャピタルゲイン(値上がり益)」、企業が上げた利益の一部を受け取れる「インカムゲイン(配当金など)」の両方を追求できる点にあります。購入した銘柄の株価が上昇すれば売却益を得られ、安定した収益力を持つ企業であれば配当を長期的に受け取ることも期待できます。
株式には、企業の業績、経済状況、金利動向、世界情勢など多岐にわたる要因によって価格が変動するリスクがあります。そのため、短期的な値動きに一喜一憂せず、企業の将来的な成長性を見極め、長期的な視点での投資が必要となります。
株式投資は中長期的な資産形成の有力な手段ですが、複数の銘柄に分散投資するといったリスク管理を行い、自身のリスク許容範囲を超えないよう慎重に取り組むことが求められます。
債券とは、国や地方公共団体、企業などが資金を調達するために発行する有価証券です。投資家は債券を購入することで、発行している組織にお金を貸す形になります。
債券は、満期まで保有すればあらかじめ決められた利息(クーポン)と元本が返ってくる仕組みで、国が発行する国債、自治体が発行する地方債、企業が発行する社債などが代表的です。
株式に比べて価格変動の幅が小さく、比較的元本の安全性も高いため、安定性を重視する方に向いている方法といえますが、債券の発行元が財政難や経営不振に陥れば、元本や利息が支払われないリスク(信用リスク)も存在します。
また、債券も市場で売買されるため、金利の変動によって価格が上下する価格変動リスクが存在し、キャピタルロスが発生する可能性もあります。
債券には個人向け国債のように1万円などの低額から購入できる商品もあるため、初心者でも取り入れやすい資産形成手段の一つです。
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ、ファンドマネージャーと呼ばれる専門家が、株式や債券などに分散して投資を行う金融商品です。
投資信託はキャピタルゲイン(値上がり益)とインカムゲイン(配当収入)の両方が期待できます。投資家自身が個別に銘柄を選ぶ必要がなく、専門家が自分の代わりに運用してくれるため、初心者にも始めやすい点が魅力です。
また、投資信託には特定の指数(日経平均株価、S&P500など)に連動する「インデックスファンド」と、市場平均を上回る成果を目指す「アクティブファンド」の2種類があります。一般的に、インデックス型は運用コストが低く、アクティブ型は高くなるのが特徴です。また、統計的には、多くのアクティブファンドがインデックスファンドのパフォーマンスを下回るとされています。
投資信託は、数ある手段の中でも少額から購入可能な金融商品であり、積立投資にも対応しているため、長期的な資産形成にも適しています。積立投資のしやすさから、NISA(少額投資非課税制度)でも積極的に活用されています。

金(ゴールド)への投資は、代表的な実物資産投資の一つであり、金融危機やインフレ時にも価値が下がりにくい安全資産として知られています。コモディティは「商品」を意味する言葉で、金以外にもプラチナなどの貴金属、原油などのエネルギー、小麦・とうもろこしといった農産物など、実物資産を指します。
金は世界共通の価値を持ち、通貨のように国の信用に依存しないため、不安定な相場や地政学リスクへのヘッジ手段として多くの投資家から好まれている金融資産です。
金に対する投資方法にはいくつか種類があり、金地金(インゴット)や金貨など現物を購入する方法の他、金価格に連動するETF(上場投資信託)や純金積立などがあります。
なお、金は預貯金でいう利息はなく、株式のように配当も生まないため、売買によるキャピタルゲインのみを狙う金融商品です。価格変動リスクもあるため、投資する際はリスク許容度や資産配分を考慮する必要があります。
不動産投資とは、アパートやマンションなどの収益物件を購入し、入居者に賃貸して家賃収入(インカムゲイン)を得ます。また、購入した不動産の価格が上昇した際に売却することで得られる利益(キャピタルゲイン)も期待できます。
他の資産運用方法と異なる特徴として、金融機関からの融資を活用できる「レバレッジ効果」が挙げられます。自己資金以上の規模で投資を行い、効率的なリターンを目指せる点が大きな強みです。
また、条件を満たせば減価償却費などを計上して所得税・住民税の節税が実現できる点も、不動産投資ならではのメリットです。
不動産投資には多くのメリットがある一方で、実物資産特有のリスクも伴います。主だったものだけでも、入居者が決まらない空室リスクや、建物の維持・管理にかかる修繕費・管理コスト、地震や水害といった災害リスクなどがあります。
これらのリスクを低減し、収益性を最大化するためには、物件の立地や周辺環境、将来的な人口動態や開発計画までを見据えた物件選定が不可欠です。また、物件の資産価値を高める適正な管理が、不動産投資の成功を左右する鍵となります。

暗号資産(仮想通貨)とは、ブロックチェーンという独自の技術を利用した、インターネット上でやり取りされる実体のないデジタル通貨です。
代表的な暗号資産にはビットコインやイーサリアムがあり、中央銀行などの発行主体が存在しない点が各国の法定通貨と大きく異なる点です。種類によって価格の変動幅は異なりますが、他の金融商品に比べると値動きが大きく、ハイリスク・ハイリターンな投資対象とされています。
取引所を通じて売買されることが一般的ですが、銀行に比べてハッキングや詐欺などのセキュリティ上のリスクが高い傾向にあります。
また、国内外で規制や税制が頻繁に変化するため、常に最新情報を把握しておく必要があります。NFT(非代替性トークン)やDeFi(分散型金融)といった新たな活用領域も注目されており、技術革新の動向も含めた総合的な理解が求められます。

FX(外国為替証拠金取引)は、異なる2つの国の通貨を売買し、その際の為替レートの変動(為替差益) で利益を狙う投資方法です。
例えば、1ドル=150円の時に米ドルを買い、その後1ドル=160円になったところで売却すれば、その差益が利益となります。FXは、少ない資金で大きな金額の取引ができるレバレッジ機能を備えており、効率的な運用を可能にします。原則として月曜日から金曜日まで毎日24時間取引できるため、時間を選ばず取引できる点も魅力です。(メンテナンス時間を除く。)
FX取引では、「買い」からだけでなく「売り」からも取引を始められるため、相場の上昇局面・下落局面のどちらでも利益を狙える柔軟性があります。
FXではスワップポイントによる収益も期待できます。これは、金利の異なる2つの通貨ペアを保有して、その金利差によって日々発生する損益のことで、保有しているだけで利益(インカムゲイン)を得られるのもFXの魅力の一つです。スワップポイントについては次章で詳述します。
ここからは、FXが資産形成に有効な4つの理由を解説します。
FXは、少ない資金からでも始められる点が大きな魅力です。
取引単位はFX会社によって異なりますが、例えばSBI FXトレードでは「1通貨」から取引できるため、米ドル/円の組み合わせであれば約6円程度からスタートできます。
さらに、最大25倍のレバレッジを利用できるため、少ない自己資金で大きな金額の取引も可能です。1万円の資金でもレバレッジをかければ最大で25万円相当の取引を行うことができるため、効率的に資産を増やすチャンスが広がります。
ただし、高いレバレッジの取引は、相場が逆に動いた場合に損失も拡大します。そのため、初心者はまず少額の運用から始め、相場の仕組みや値動きに慣れることが重要です。
FXの大きな特徴の一つが、相場が下落している局面でも利益を狙える点です。
多くの投資商品では、価格が上昇しなければ利益を得られませんが、FXでは高い時に「売り(ショート)」から取引を始めて安くなったら買い戻すことができるため、価格が下落しても利益を得られる可能性があります。
具体的には、将来的にドルが円に対して下落すると予想した場合、あらかじめドルの売りポジションを取り、実際に円高が進めばその差額が利益になるのです。このように、上昇相場だけでなく下落相場でも柔軟に対応できるのがFXの魅力です。
ただし、経済指標の発表や地政学的リスクなどで相場が急変する場面ではリスクもリターンも大きくなるため、事前の情報収集やリスク管理が求められます。
月曜日から金曜日であれば、24時間いつでも取引できるという柔軟性もFXの特徴です。
株式市場は取引時間が限られており、平日の日中にしか売買できないのが一般的ですが、FXは世界中の為替市場が時差で連続的に開くため、月曜の早朝から土曜の早朝まで、原則24時間体制で取引可能です。(メンテナンス時間を除く。)
東京市場が終了するとロンドン市場、ニューヨーク市場と続くため、取引機会が常に存在しているのです。日中は仕事で忙しい会社員でも夜間に取引できるなど、さまざまなライフスタイルに合わせて柔軟に資産運用ができます。
ただし、相場参加者や取引量が少ない時間帯はスプレッド(買値と売値の差)が広がる傾向があり、思わぬ値動きをする場合があるため、時間帯別の特性を理解して取引を行うことが重要です。

FXでは為替差益(キャピタルゲイン)だけでなく、スワップポイントによってインカムゲインを得ることもできます。
スワップポイントとは、取引する2つの通貨間の金利差によって発生する調整額のことを指します。金利の高い国の通貨を買い、金利の低い国の通貨を売るポジションを保有すると、その金利差分を毎日受け取ることができるのです。
アメリカの政策金利が高く日本の金利が低い場合、米ドル買い・円売りのポジションを保有していると、レバレッジ機能が逆転しない限り毎日スワップポイントが発生します。このように、為替の値動きとは別にポジションを保有しているだけで日々収益を積み上げられるのがスワップポイントの魅力です。
逆に金利の低い通貨を買って高い通貨を売った場合や、ポジションの保有中に金利差が逆転した場合は、スワップポイントがマイナスとなり支払いが発生します。スワップポイント狙いの運用には、金利動向や通貨の特性への理解が必要です。
資産形成には、預貯金や株式、投資信託、不動産などさまざまな手法があります。効果的なリスク対策を行い、安定的に資産形成をするためには、複数の手段を組み合わせて資産を分散させることが重要です。
さまざまな資産形成の方法がある中、少額から始められ、相場の下落局面でも利益を狙えるFXは、非常に有効な資産運用手段の一つです。SBI FXトレードなら1通貨単位から取引ができるため、初心者でも無理なくスタートできます。
この機会にぜひ口座を開設して、資産形成の第一歩を踏み出しましょう。
SBI FXTRADE
FX(外国為替証拠金取引)は異なる通貨を売買し、売買時のレートによって生じた差額で利益を出そうとする取引です。
SBI FXTRADEは、スプレッドやスワップポイント、通貨ペア数など、業界最良水準のサービスをご提供しています。また、初心者の方から、上級者までご満足いただける取引ツールをご用意しております。
この記事を監修した人
SBIリクイディティ・マーケット株式会社
金融市場調査部長
上田眞理人