UPDATE 2025.09.30
POST 2025.09.30
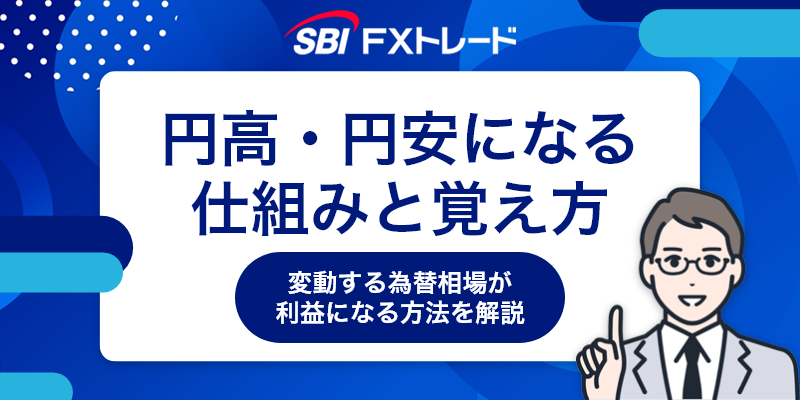
ニュースなどでよく耳にする「円高・円安」。日本円から見た為替相場の状況を表す言葉で、私達の生活にも大きな影響を与える重要な概念です。
一方で、表記から受ける印象と実際の意味が噛み合わず、「円高と円安は結局どっちが得でどっちが損なの?」と迷ってしまう人や、苦手意識を持っている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、円高や円安の意味や覚え方、為替相場が動く基本的な仕組みや理由、円高や円安が私達の生活にどのような影響を与えるのかなどを網羅的に解説します。
FXで為替の変動を利益にする仕組みもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
米ドルやユーロなど、異なる国の通貨を交換する取引を「外国為替取引」、この交換比率を「為替相場」と呼び、相場は日々変動しています。
まずはこの為替相場における円高・円安について解説します。

円高とは、日本円の価値が外国の通貨に対して高くなる現象を指します。
例えば、以前は1ドル=150円だったのに、現在は1ドル=100円になっている場合、同じ1ドルをより少ない円で買えるということです。これは「日本円の価値が上がった」といえる状態なので「円高」といいます。
円高になると、外国製の衣類やスマートフォン、原油などの仕入れコストが抑えられるため、海外からの輸入品の価格が下がり、輸入企業の利益が上がりやすくなります。個人の消費者にとっても、海外旅行の費用が安くなったり、海外通販の価格が下がったりと、生活面でのメリットが大きくなります。
一方で、輸出企業にとって不利となります。円高になると海外から見た日本製品の価格は割高になり、他国製品との価格競争で勝てなくなる可能性があるからです。
このように、円高は「円の価値が上がっている状態」を指しますが、その影響は立場によって大きく異なります。

円安とは、円高とは逆で「日本円の価値が外国の通貨に対して下がっている状態」を指します。
例えば、以前は1ドル=150円だったのに、現在は1ドル=200円になっている場合、同じ1ドルを得るためにより多くの日本円が必要になります。これは「日本円の価値が下がった」といえる状態なので「円安」といいます。
円安になると、ガソリンや食料品、スマートフォンなどの海外からの輸入品の価格が上昇するため、輸入企業にとっては仕入れコストが増加します。個人の消費者にとっても生活費が上がる原因となり、日常の家計に直接的な影響が及ぶ可能性があります。
輸入に頼っている商品・製品が多い日本では、円安になると物価全体が上昇しやすく、インフレ傾向が強まるおそれもあります。
一方で、輸出企業にとっては有利となります。円安になると日本製品の価格が相対的に安くなるため、海外市場での競争力が高まり、輸出企業の利益が増えやすくなるのです。

ニュースで「円高」や「円安」という言葉を耳にするたびに、どちらがどういう状態なのか混乱してしまう人は少なくありません。
その理由の1つが、為替レートの表記方法にあります。為替は「米ドル/円」の形で表示されるのが一般的です。そのため、「1ドル=150円」が「1ドル=170円」になると、日本円の数字が増えたことで円の価値も上がったと錯覚しやすくなります。
しかし、実際は「1ドルを得るために必要な円が増えている」という意味なので、円の価値が下がっている状態、つまり「円安」を意味します。
逆に「1ドル=150円」から「1ドル=130円」になれば、「1ドルを得るために必要な円が減っている」という状態なので、日本円の価値が上がっている状態、つまり「円高」となります。
このような混乱を避けるには、「米ドルが上がると円安、米ドルが下がると円高」と覚えるのが効果的です。レートの数字は米ドル側が動いていると考えると、判断がしやすくなるでしょう。
国の通貨の価値は相対的な評価で決まります。自国通貨を外国の通貨に換える際の比率は常に変動しており、これを「変動相場制」と呼びます。
為替相場が変動する背景には、金利や貿易収支、物価の変化などさまざまな要因があります。
為替相場が変動する理由のうち、中長期的な要因としては、「各国の金利の差」「貿易収支の黒字や赤字」「物価の変動」などが代表例です。
これらの経済要素は、国の信用力や財政の安定性、将来的な経済成長への期待と深く関わっており、長期間にわたって通貨の価値にさまざまな影響を及ぼします。
為替相場における重要な中長期的要因の一つが、各国の金利の差です。
金利が高い国の通貨は投資家からの需要が高まり、多く買われることでその通貨の価値が上昇しやすくなるためです。
例えば、日本の金利が低く、アメリカの金利が高い場合、高い利回りを求めて米ドルを買う人が増え、利回りの低い日本円は売られる傾向が強まることで、結果的にドル高・円安が進行します。逆にアメリカの金利が下がれば米ドルの魅力は相対的に下がり、円高に動く可能性も出てくるでしょう。
このように金利差によって生じる国際的な資金移動は、為替相場の長期的な方向性を決定づける重要な要因とされており、各国の金融政策の変化は常に市場から注視されています。

貿易収支とは、ある国が一定期間に輸出した金額と輸入した金額の差額を指します。
貿易収支は、為替相場に中長期的な影響を与える重要な経済指標の1つで、輸出が輸入を上回ると貿易黒字、逆に輸入が多ければ貿易赤字です。
例えば、日本が多くの製品を海外に輸出すれば、それによって得た外貨を日本円に換える必要があるため、日本円の需要が高まることで円買いが進行しやすくなります。一方、エネルギーや原材料の輸入が増えれば、輸入業者は外貨を調達するために日本円を売却し、円安が進む可能性があるのです。
また、貿易収支はその国の産業構造や国際競争力を反映する側面もあり、通貨の長期的な価値を判断する上で有力な参考指標となります。
ただし近年は、投資資金の移動や資本収支の動向など、複数の要因が複雑に絡んでいるため、貿易収支だけで為替の動向を読み解くのは困難です。
物価の変動も為替相場に影響を与える重要な要素です。
一般的に、インフレが進んで物価が上昇すると、通貨の購買力(ものを買う力)が低下し、その通貨の価値は相対的に下がってしまいます。その結果、通貨は売られやすくなり、為替市場では通貨安が進行しやすくなります。
例えば、日本で短期間に物価が急上昇し、米国では物価が安定している場合、日本円の価値は相対的に下がり、米ドルに対して円安になる可能性があります。反対に、物価が安定している国の通貨は市場や投資家から信頼されやすく、投資先として選ばれる傾向があります。
さらに、物価の動向は中央銀行の金融政策や市場の期待とも密接に関係しています。特にインフレ率の急激な上昇は通貨安を招く懸念材料になるため、為替市場に大きな混乱を引き起こす場合もあります。
こうした理由から、為替相場を読み解く上で物価の変動は極めて重要な判断材料になり得ることから、日常的に注目しておく必要があるでしょう。
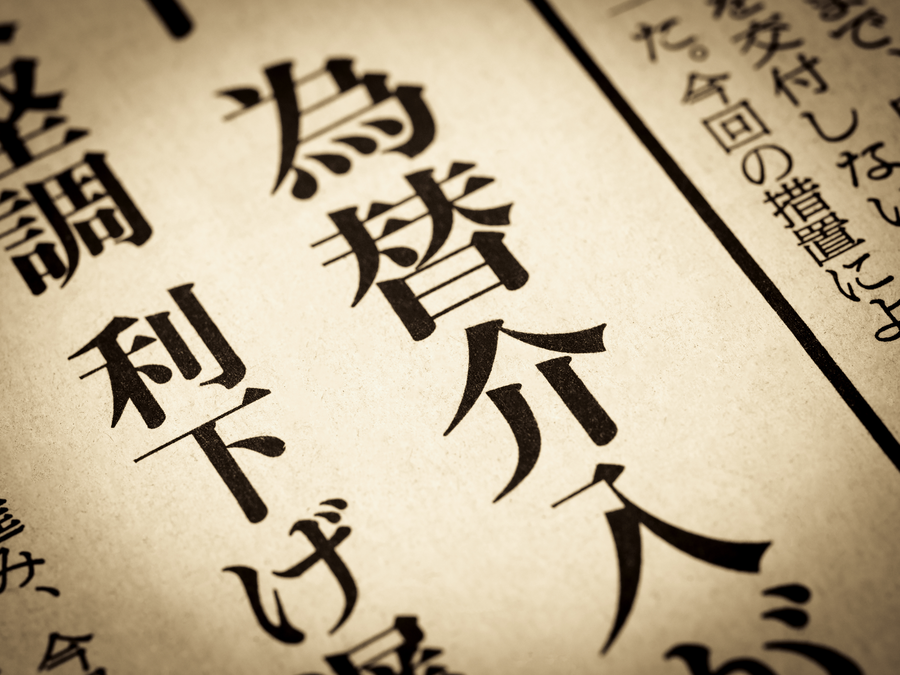
為替介入とは、急激な為替変動を抑えるために、政府・中央銀行が市場で通貨の売買を行う政策手段です。
例えば、急激に円安が進んだ場合、日本銀行が日本円を買って米ドルを売ることで、為替相場を円高方向に戻そうとします。
前述の通り、為替相場は輸出入する物の価格にも大きな影響を与えます。特に日本はエネルギーや食料などの多くを輸入に頼っているため、為替相場の急変は輸入品の物価や企業活動に大きな影響を与えかねません。そのため、為替相場の変動による影響を抑えるために為替介入が行われる場合もあります。
また、為替介入は事前の発表なく突発的に実施されるケースが多いため、市場にとってはサプライズ要因となり、相場が急変するきっかけにもなります。実際に、2022年には日本政府が24年ぶりにドル売り・円買い介入を実施していますし、2024年にも大規模な「覆面介入」を実施したと見られています。
このように、政府・中央銀行による為替介入は、短期的かつ大きな為替相場の変動のきっかけになりやすい出来事です。
重要な経済指標が発表されると、為替相場は短期的に大きく変動する場合があります。
具体的には、米国の雇用統計や消費者物価指数(CPI)、GDP成長率などが挙げられます。これらの指標は市場参加者から常に注目されているため、発表された数値が市場予想と大きく異なっていた場合、それがサプライズとなって為替相場が急変する場合があります。
中でも、米国の経済指標はドル相場に大きな影響を与えるため、世界中の投資家が注視しています。日本や欧州などの経済指標も同様に重要視されており、なかでも政策金利の見通しに関係する要素が含まれる場合は、その影響力は一層大きくなります。
経済指標の発表前後は値動きが激しくなる傾向にあり、数分で数円程度変動するケースも珍しくありません。そのため、FX取引を行う際は重要な経済指標の発表スケジュールを事前に確認しておくことに加えて、発表前後の取引はより慎重に行うことが大切です。
為替相場は、各国政府の要人の発言によって大きく動くことがあります。
例えば、財務大臣や中央銀行総裁が、為替の水準について「容認できない」「行き過ぎている」といった発言をした場合、市場は為替介入や政策変更の可能性を警戒し、為替相場が急変することがあります。
特に米国のFRB議長や日本銀行の総裁など、金融政策を担う要人の言動は特に注目されており、為替相場も発言内容に敏感に反応します。発言の内容だけでなく、発表されたタイミングや発言に至った背景、過去の発言との整合性、経済状況との関係性なども考慮されるため、解釈の違いによって市場が一方向に大きく動く場合もあります。
このように、政府要人の発言の読み取りは、為替相場の短期変動を予測する上で欠かせない要素のひとつです。
地政学リスクとは、国家間の対立や戦争、テロ、政変、領土問題などによって、世界経済や市場に不確実性が生じる状況を指します。
為替相場はこのような地政学リスクに対して非常に敏感で、安全資産とされる日本円・米ドル・スイスフランなどに資金が流れ込む傾向があります。
例えば中東での軍事衝突、ウクライナ情勢の悪化、台湾海峡での緊張の高まりなどが報じられると、投資家は地政学リスクを避けようと安全通貨を買うため、結果的に円高やスイスフラン高が進行するのです。
逆に、地政学リスクの緩和が確認されれば、比較的リスクが高い資産にも資金が分散され、為替相場が反転することもあります。
ただし、地政学リスクは突発的に発生するケースが多く、予測が難しい要素でもあります。FX取引を行う際は、日々の国際ニュースや地域情勢の変化をこまめにチェックし、地政学リスクを徹底することが重要です。
円高・円安は、私たちの生活にも深く関わっています。ここからは、為替相場の変動によるメリットとデメリットを解説します。

円高は、他国の通貨に対して日本円の価値が高くなる現象を指し、私たちの生活にさまざまなメリットをもたらします。
例えば、原油や天然ガスなどのエネルギー資源や食料品を海外から輸入する際、日本円の価値が高ければ高いほど安く調達できます。これによって、ガソリンや食品などの日常生活に欠かせない輸入品が安く手に入るため、私達の生活費の節約につながります。
また、海外ブランドの商品や電化製品なども安く入手できるため、輸入小売業者にとっては仕入れコストが下がり、消費者は高品質な商品をより安価で購入できるようになります。他方で、大企業は海外企業の買収や現地拠点への投資額を抑えられるといったメリットもあります。
さらに、円高は海外旅行にも好影響です。海外旅行にかかる費用を抑えられるため、そもそも海外旅行に行きやすくなります。加えて、両替時に得られる外貨が増えるため、旅行先での選択肢が広がる点もメリットです。
円高は輸入や海外旅行には有利に働く一方で、輸出や観光業などにはさまざまなデメリットがあります。
例えば、日本国内で製造した製品を海外に輸出する場合、輸出先にとっては仕入れ価格が高くなるため、他国との価格競争力が低下します。その結果、日本の製品が海外で売れにくくなり、輸出企業の売り上げや利益が圧迫される可能性があります。なかでも、自動車や電機製品などの輸出依存の高い大企業では、業績が悪化するケースも珍しくありません。
また、外国人観光客から見ると日本への旅行費用や物価が割高に見えて訪日意欲が下がります。これにより、ホテル・飲食店・土産物店など地域経済を支える観光産業の売り上げが落ち込んでしまいます。輸出企業や観光業の業績悪化が日本全体の景気後退の引き金となり、企業の賃金や雇用環境の悪化につながる場合もあるでしょう。
このような負のスパイラルが、消費者の所得減少や家計の圧迫を招くケースもあるのです。

円安は、輸出企業や観光業を中心に多くのメリットをもたらします。
日本国内で製造された製品を海外で安く販売できるようになるため、価格競争力が高まることで輸出が活性化し、輸出企業の売り上げや利益率の向上が期待できます。特に、自動車・電子機器・精密機械・化学製品など、輸出が中心の大手企業にとって円安は大きな追い風となり、売り上げや利益の増加が見込めます。
また、外国人観光客にとって日本での買い物や旅行が割安に感じられるようになるため、インバウンド需要が拡大します。これにより、ホテル・飲食・商業施設・交通などの幅広い業界が潤い、地域経済の活性化にもつながるのです。
さらに、企業の収益が改善されれば、株価の上昇や雇用環境の改善、消費者の所得増加なども期待できるため、消費が刺激され、日本全体の景気回復を後押しする好循環が生まれる可能性があります。
円安が進行すると、日本の通貨である日本円の価値が下がり、外国からの輸入品の価格が上昇します。
これは原材料・食品・エネルギー資源などを海外から仕入れている企業にとってコスト増につながります。特に中小企業や個人経営の商店では価格転嫁が難しく、経営を圧迫する大きな要因にもなり得ます。
さらに、企業の仕入れコスト上昇は最終的に商品やサービスの価格に反映されるため、消費者の家計にも直接的な影響を与えます。具体的には、ガソリン・電気・ガス・食料品・日用品などの生活必需品が値上がりし、全体の物価が上昇する恐れがあります。
また、円安は日本人にとって海外旅行の費用が割高になることを意味します。現地で使える金額が目減りし、ホテルやレストラン、買い物などで出費がかさむため、海外旅行そのものを見送る人も増えるでしょう。
このように、円安は特定の企業や業種だけでなく、私たち国民生活全体にまで広く負担をもたらす要因となるのです。
FXでは、為替レートの変動によって生じる「為替差益」と、金利差から得られる「スワップポイント」という2種類の仕組みで利益を得られる可能性があります。
為替差益とは、通貨の売買によって生じる差額から利益を得る仕組みです。
FXでは「安く買って高く売る」または「高く売って安く買い戻す」ことで利益を得ることができ、これを「キャピタルゲイン」と呼びます。
例えば米ドル/円の相場が上がると予想した場合は「買い(ロング)」から取引を始め、実際に相場が上がった時に売ればその差額が利益になります。逆に、相場が下がると予想した場合は「売り(ショート)」から入ることも可能です。
このように、為替の上下動どちらでも利益を狙えるのがFXの特徴です。以下では円高・円安それぞれの具体的な取引例をご紹介します。
相場が円高になると予想した場合、FXでは米ドル/円の「売り」から取引を開始します。
例えば1ドル=150円のときに米ドルを売り、その後1ドル=140円になった時点で買い戻せば、10円の為替差益を得ることができます。
このように、日本円の価値が上がると予想した場合は「売り」から取引を始めることで利益を狙えるのです。
相場が円安になると予想した場合、FXでは米ドル/円の「買い」から取引を始めます。
例えば1ドル=140円のときに米ドルを買っておき、その後1ドル=150円に上昇したタイミングで売却すれば、10円分の差益が得られます。
円安局面では「買い」から取引を始め、相場の上昇によって利益を得ることができるのです。
このように、FXでは円高・円安いずれの場合も利益を得られる可能性があるのが大きな特徴であり魅力です。
スワップポイントとは、FX取引において通貨間の金利差に基づいて発生する調整額のことです。
特定の通貨ペア(ポジション)を保有している間、金利の低い国の通貨を売り、金利の高い国の通貨を買うことで、その金利差に相当するスワップポイントを受け取ることができ、これがFXにおける「インカムゲイン」となります。
具体的には、アメリカの政策金利が5%台、日本が0%前後だった場合、米ドル/円の買いポジションを保有すれば、比較的多額のスワップポイントの受け取りを期待できます。
このスワップポイントの仕組みがあるため、FX取引では為替差益を狙うだけでなく、金利差による安定的な収益を目指す中長期投資家にも支持されています。
ただし、金利差が縮小または逆転した場合は、スワップポイントによる受け取り額が減るだけでなく、逆に支払いが発生することもあるため注意が必要です。スワップポイントは毎日変動するため、最新の情報を確認しながら取引することが重要です。

ここからは、円高・円安の今後の見通しについて、さまざまな視点から解説します。
円高か円安か、どちらに向かうのかは、多くの要因が複雑に絡み合っており、現時点で断定することは困難です。
過去の事例として2024年前半までは急速な円安が進行していましたが、最近では日米の金利差が縮小傾向にあることから、円安の勢いには一時的なブレーキがかかっていると見られています。
ただし、今後の為替相場は世界経済の成長鈍化やインフレ率の変動、地政学的リスク(中東や東アジアにおける軍事的緊張など)など、予測が困難な事象によって大きく変動する可能性があります。
特に、トランプ米大統領の関税政策や金融政策は注目されるポイントです。加えて、FRB(米連邦準備制度理事会)や日本銀行の声明なども市場心理に強い影響を与えるため、定期的な発信内容のチェックも欠かせません。
このように、為替相場の動きはさまざまな不確定要素が絡み合って変動するため、残念ながら確かなことは言えないというのが実情です。
日本銀行が政策金利を引き上げるかどうかは、今後の日本経済や金融市場の動向を大きく左右する極めて重要な判断材料です。
これまで日銀は、デフレからの脱却や景気への刺激を目的として、マイナス金利を含む異例の金融緩和策を粘り強く続けてきました。しかし最近では、原油価格の高騰や円安の進行、人手不足を背景とした賃金の上昇といった複合的な要因により、消費者物価指数は上昇を続け、目標としていた2%が達成された状態です。
こうした環境の変化を受け、日銀は段階的な利上げ、つまり「金融政策の正常化」を一段と進める可能性があります。
今後は、企業のベースアップの動きや家計の消費動向、為替相場の推移、さらに米欧の中央銀行の対応など、あらゆる要因を踏まえて慎重に政策判断が行われることになるでしょう。
大規模な戦争や国際的な軍事衝突が発生すると、為替相場にも大きな影響を及ぼします。
例えば、ロシア・ウクライナ戦争や中東情勢の悪化といった地政学リスクが高まる局面では、投資家は比較的安全とされる通貨や資産に資金を逃避させる傾向にあり、このような動きは「リスクオフ」と呼ばれています。
地政学リスクが高まっている状況で買われやすいのが、米ドルやスイスフランなどの国際的な信用力の高い通貨です。かつては日本円も「安全通貨」として扱われていましたが、現在では長期にわたる超低金利政策や日本経済に対する構造的な不安、財政赤字の拡大、人口減少などが複合的な不安要素となり、リスクオフの場面でも円が買われにくくなってきました。
このような背景から、今後も万が一大規模な戦争が発生した場合でも、為替市場ではドル高・フラン高が進行し、円の買いは限定的にとどまる可能性が高いと見られています。
円高・円安のどちらに動いても利益を狙えるのがFXの魅力です。買い(ロング)だけでなく、売り(ショート)からでも取引ができるため、為替相場がどちらに動いてもチャンスがあります。
為替の仕組みを正しく理解すれば、リスクを抑えながら収益を目指すことも可能です。はじめてのFXには、業界最狭水準のスプレッドや1通貨単位から取引できる「SBI FXトレード」がおすすめです。少額からスタートできるため、初心者でも安心して始められます。
この機会にぜひ口座開設を検討してみて下さい。
SBI FXTRADE
FX(外国為替証拠金取引)は異なる通貨を売買し、売買時のレートによって生じた差額で利益を出そうとする取引です。
SBI FXTRADEは、スプレッドやスワップポイント、通貨ペア数など、業界最良水準のサービスをご提供しています。また、初心者の方から、上級者までご満足いただける取引ツールをご用意しております。
この記事を監修した人
SBIリクイディティ・マーケット株式会社
金融市場調査部長
上田眞理人