UPDATE 2025.08.26
POST 2025.08.26
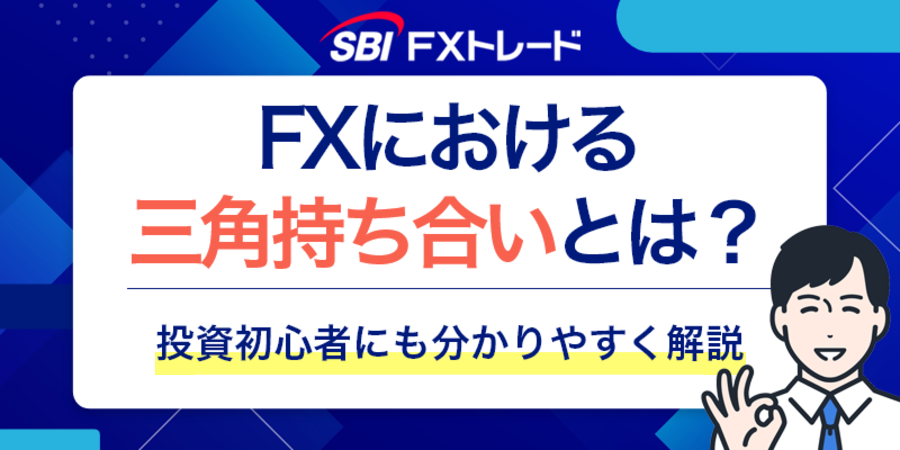
取引スキルのレベルを問わないチャートパターン分析の一つである三角持ち合いは、多くのトレーダーに人気のある分析手法です。FX初心者の中にも、「なぜ三角持ち合いができるの?」「ダマシを回避する方法が知りたい」と気になっている方がいるのではないでしょうか。
三角持ち合いは、うまく利用できれば大きな利益を得ることが可能です。しかし、ダマシなどの紛らわしいパターンもあるため、正しく理解しなければ損をするケースも少なくありません。取引に慣れていないFX初心者は、まず仕組みを理解した上でデモトレードなどを試し、実際のコツをつかんでから取引を始めることが大切です。
本記事では、三角持ち合いの基礎知識やFX取引に利用する際のメリット・デメリットを始め、エントリー・利確・損切りのポイントなどを解説します。この機会に三角持ち合いの知識を身に付け、取引に活かしてみて下さい。
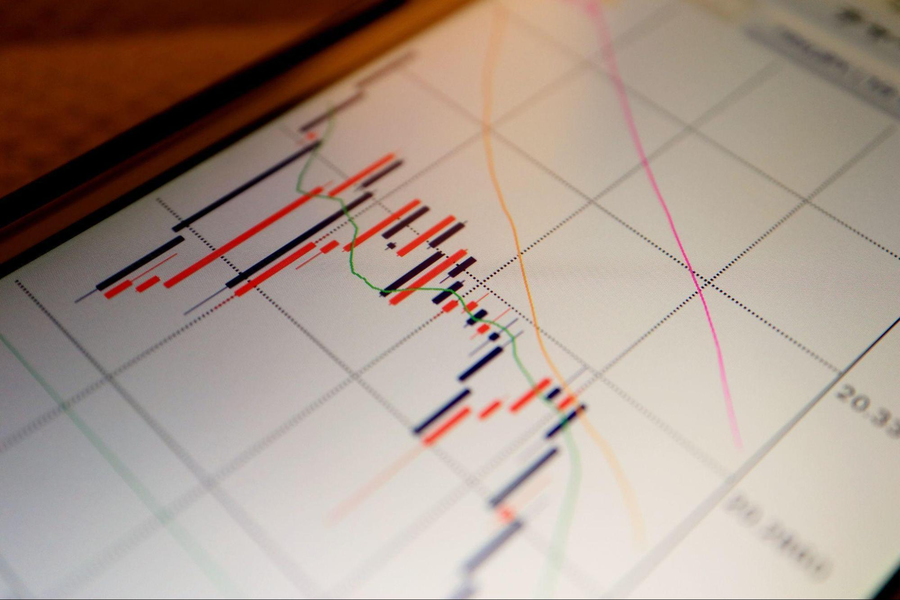
FXにおける三角持ち合いとは、簡単にいうと、高値と安値を結んだラインで形成される三角形のチャートパターンのことで、トライアングルと呼ばれることもあります。
価格変動が一定の範囲で継続している状態を「持ち合い」といいます。三角持ち合いは、価格の上昇・下落の幅が徐々に狭まっていくことで、チャートの形が三角形になるパターンをいいます。
一般的に、三角持ち合いができている状態は、買い注文と売り注文が競り合っているため、どちらか一方のラインをブレイクすると、その方向に大きく動く傾向があるといわれています。
なお、三角持ち合いは1本のトレンドラインとサポートライン、レジスタンスラインによって構成されます。
サポートラインとは下値支持線ともいい、過去の安値と安値を結んだ線のことです。これ以上は下落しないことを示すラインであり、チャートの下部に引くことで、安値の目安として使われます。
一方、レジスタンスラインは上値抵抗線ともいい、価格の上値を抑えているラインです。このライン付近まで値上がりすると売り注文が増え、上昇から下降に転換する可能性があります。
また、三角持ち合いはさまざまな時間足によく出現するチャートパターンであることも覚えておきましょう。日足(日単位の値動きを1本のローソク足で表したもの)ではトレンドが安定していたとしても、4時間足・1時間足では三角持ち合いになったり、逆のパターンになったりすることも頻繁に発生します。
さらに、三角持ち合いはラインブレイクをすると大きな利益を狙える一方で、ダマシが発生することも多いため、ダマシとブレイクを見分けることが重要です。ダマシについては後述します。
とはいえ、三角持ち合いの基礎知識や分析方法が分かっても、FX初心者の中には最初どのように活用すれば良いか悩んでしまう方もいるかもしれません。FX初心者が三角持ち合いを活用する際のポイントは、以下の3点です。
きれいな三角形になっているチャートは、多くのトレーダーが「三角持ち合い」と判断します。そのため、大きなブレイクになりやすい傾向があります。つまり、FX初心者にとっても読みやすいチャートであるということです。
三角形の形が崩れていると、当然ながら三角持ち合いと判断しないトレーダーが出てきます。そうなるとチャートの動きが不規則になり、ブレイクもしにくくなるので、失敗する確率が高まってしまいます。そのため、なるべくきれいな形をしている三角形を狙いましょう。
自分のトレードスタイルに合った三角持ち合いを探すことも大切です。三角持ち合いと一言でいっても、小さい三角形から大きい三角形まで、さまざまな大きさの三角持ち合いがあります。そのため、ポジションの保有期間が最も短い「スキャルピング(数分〜数十分で完結する超短期売買)」で取引するなら、5分足や15分足といった短い時間軸に現れる小さい形の三角持ち合いを狙うのが効果的です。
一方で、ポジションの保有期間が長く、大きな値幅を狙う「スイングトレード(数日〜数週間ポジションを保有)」なら、1時間足〜日足レベルで形成される大きい形の三角持ち合いを使うほうが理にかなっています。自分のトレードスタイルに合わない三角持ち合いを選ぶと、期待した動きが出る前にロスカットされるなど、失敗する可能性が高くなるので注意しましょう。
同じチャート上に複数の三角持ち合いがある場合、どの時間足のパターンを信頼すべきかという問題があります。基本的には、長い時間足の三角持ち合いを優先させることを意識しましょう。FXでは一般的に、短い時間足よりも長い時間足の方が信頼性が高く、値動きの方向性を決めやすいとされています。適切な時間足はトレードスタイルによっても異なりますが、基本的には最も長い時間足の三角持ち合いを優先することを意識しましょう。
また、上位足の流れが下位足のブレイクに影響を与えることも大切なポイントです。たとえば、1時間足で上昇トレンドが続いており、15分足で上方向に三角持ち合いをブレイクした場合、その動きは「トレンドに沿ったブレイク」とみなされ、勝率の高いエントリーポイントになる可能性が高まります。
三角持ち合いには、以下3つの種類があります。
次項でそれぞれ詳しく解説します。
アセンディング・トライアングル(上昇型)は、高値が一定の価格水準で止められつつ、安値が徐々に切り上がっているときに現れるチャートパターンです。上値を押さえる水平なレジスタンスラインと、安値を結ぶ右肩上がりのトレンドラインによって、上に開いた三角形のような形が作られます。
このパターンは、市場で買い圧力が徐々に高まっていることを示しており、最終的にレジスタンスラインを上抜ける=上方向にブレイクアウトしやすいとされます。ただし、必ずしも上にブレイクするとは限りませんので、上昇目線で見つつ、下落した場合の対策を考えておくことが大切です。とくに、市場全体が弱気トレンドにある場合や、ファンダメンタルズが悪化している場合は、下方向にブレイクする「失敗型」もあり、上昇トレンドは終了したことになります。
取引中に、下降トレンドや持ち合いから上昇トレンドに転換することを「ブレイクアップ」と呼びますが、アセンディング・トライアングル(上昇型)をトレードに活用する場合、レジスタンスラインを明確にブレイクアップするのを待ってからエントリーするのが一般的です。
アセンディングトライアングル(上昇型)は、特にテクニカル分析を行うトレーダーに注目されているパターンで、レジスタンスラインとトレンドラインが収束するポイントが近付きブレイクアウトが予想される場合、多くのトレーダーがエントリーポイントを探る展開となるでしょう。
ディセンディング・トライアングル(下降型)は、安値が一定の価格水準で下げ止まりつつ、高値が徐々に切り下がっているときに現れるチャートパターンです。見た目には、水平に一定のサポートライン(下)と右肩下がりに切り下がってくるトレンドライン(上)の2つのラインが交差してできる「下向きに尖った三角形」が作られます。
このパターンは、アセンディングトライアングル(上昇型)の逆で、買い手の防衛ライン(=サポートライン)は維持されているものの、売り手が徐々に強くなっていて、高値がだんだん低くなっているという状況を示しています。やがて、買いの勢いが尽きると、サポートラインを下にブレイクして下落トレンドが加速するケースが多いとされています。
このパターンも、確率的に下落しやすい形ではあるが、100%ではありません。とくに、全体の相場環境が強気トレンドの場合や、重要な経済指標の発表直前などは、「ダマシ上げ」が発生することもあるため要注意です。
上抜けしてしまった場合は「逆三角持ち合い失敗型」として、買いサインに転じることもあるため、一方向に思い込みすぎない姿勢が大切です。
ブレイクアップとは反対に、上昇トレンドや持ち合いから下降トレンドに転換することを「ブレイクダウン」と呼びます。ディセンディング・トライアングル(下降型)の場合、サポートラインが明確にブレイクダウンするのを待ってエントリーするのが一般的なトレード手法です。
ディセンディング・トライアングル(下降型)の場合、視覚的に「上値がどんどん重くなっている」ことがわかりやすいため、アセンディングトライアングル(上昇型)よりも早い段階で下落することも少なくありません。とくに、トレンド全体がすでに下落方向、ファンダメンタルズに悪材料が出ている、直前の反発が弱く、「買い意欲が続かない」雰囲気があるなどのケースでは、早めの下抜けが起こりやすくなります。ただし、マーケット状況によってはアセンディング型の方が早くブレイクしたり、動き出しのタイミングは変わってきます。
つまり、「下降型だから必ず早く崩れる」というのは一般論としての傾向にすぎず、パターン単体では断言できないというのが現実的な見方です。
シンメトリカル・トライアングル(均衡型・対称三角持ち合い)は、安値が徐々に切り上がる上昇トレンドラインと、高値が徐々に切り下がる下降トレンドラインが同時に進行し、価格が徐々に収束していく、対称的な三角形のチャートパターンです。
このパターンは、買い手と売り手の勢力が拮抗している状態であるため、どちらにもブレイクする可能性があり、どちらかに勢いがつくと、大きく価格が動く可能性が高いのが特徴です。時間足は、4時間足や日足で確認するとノイズが少なく、信頼性が高くなります。
シンメトリカル・トライアングル(均衡型)は、ブレイクする方向がチャート形状だけでは予測できないため、他のテクニカル指標やファンダメンタルズ分析などを活用し、上昇するのか下降するのか見極める必要があります。ただし、経済指標の発表時などは信頼性が低下し、トレンドが明確でない相場では機能しにくいこともありますので、注意が必要です。
このように、三角持ち合いには3つのチャートパターンがあり、それぞれに合った戦略で取引することが大切です。

以下の3つは、三角持ち合いに似ているチャートパターンです。
ペナントは、短期間の調整で現れる旗型チャートパターンで、強い上昇トレンド、または下降トレンドの一時調整後に出現します。ペナントの特徴は、高値と安値の差が狭まり、三角形に似た形状をつくり出すことで、ブレイク後の伸びが大きく、スキャルピングやデイトレに最適です。
ペナントは、トライアングルとは異なりトレンドの継続が予測され、一時調整後は価格がトレンド方向に抜ける動きが見込まれます。ペナントには上昇ペナントと下降ペナントの2種類があります。
上昇ペナントは上昇トレンドの途中に発生するパターンで、多くの場合、三角形の上部を抜け出す動きが見込まれ、その後上昇トレンドが継続します。
下降ペナントは上昇ペナントの逆で、下降トレンドの途中で発生し、多くの場合、三角形の下部を抜け出す動きが見込まれ、その後下降トレンドが継続します。
ペナントは、他のテクニカル分析や指標と組み合わせて使用されることが多く、市場の動向を分析する際に参考にするパターンとして知られています。
上昇ウェッジとは、高値と安値がどちらも同じ向きに切り上げながら徐々に幅が狭くなっていくチャートパターンのことで、基本的にはトレンドの失速・反転シグナルとして出現します。
上昇ウェッジは、上昇トレンドの天井圏で発生しやすく、高値更新しているのに勢いがなく、出来高が減少しているような状況の時には警戒が必要で、下方向へのブレイクが発生すると、強い反落に発展しやすいことを示します。
下降トレンドの途中、一時的な調整で上昇ウェッジが形成されることもあります。このパターンが出現すると、上昇トレンドに切り替わると予想しがちですが、トレンドは変わらず続く傾向があります。
下降ウェッジは上昇ウェッジの逆で、高値と安値がどちらも同じ向きに切り下げながら、徐々に幅が狭くなっていくチャートパターンで、こちらも基本的にはトレンドの失速・反転シグナルとして出現します。
下降ウェッジは、安値圏から上昇方向に転換する場合に出現しやすいチャートパターンで、安値更新しているのに下げ幅が縮小して下ヒゲが多いような状況の時は転換の兆しであり、上に抜ければ、買いエントリーの好機になることが多いと考えられます。
上昇トレンドの途中、一時的な調整で下降ウェッジが形成されることもあります。このパターンは上昇トレンドにもかかわらず、安値と高値がそれぞれ切り下がっており、下降トレンドへの転換に見えがちですが、やはり上昇トレンドが継続する傾向があります。
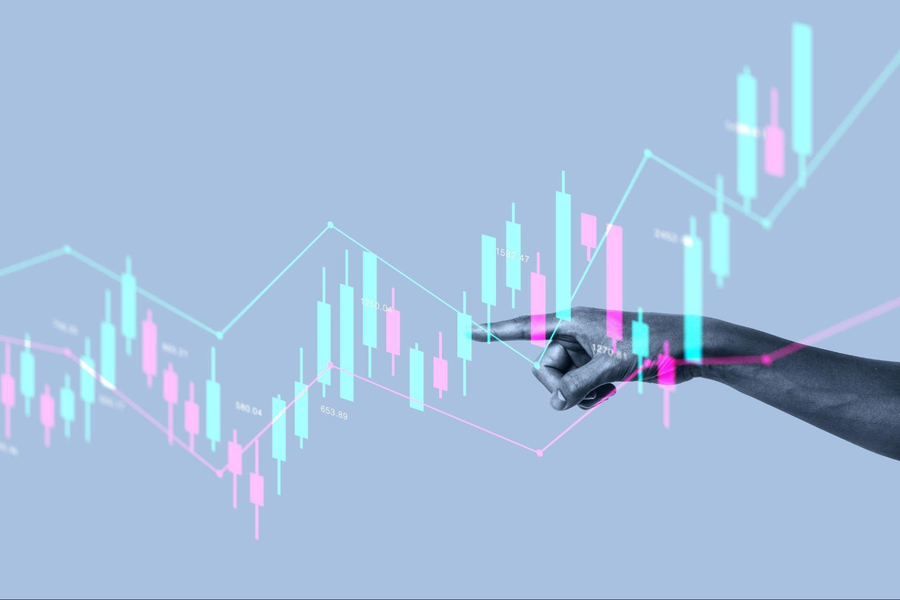
チャート上で三角持ち合いのトレンドラインを引く場合、レンジ相場の中で幅が狭まっていることが前提にあります。レンジ相場とは、一定の高値と安値の範囲内で価格が推移する動きのことです。
つまり、三角持ち合いは、上下幅が大きいレンジ相場の中で上値が切り下がり、下値が切り上がって徐々にレンジ幅が狭くなっている時に引くことができます。逆に、上値が切り上がり、下値も切り上がっている時は引けません。
また、トレンドラインを引く時は、できるだけ多くの上値・下値を結ぶことが重要です。2つや3つだけのポイントでは信頼性は低くなります。
レンジ相場の中で幅が狭まっていることに気が付いたら、三角持ち合いのトレンドラインを引いてみましょう。何度も引くことで、値動きを予測しやすくなります。

三角持ち合いのブレイクを狙った取引は、エントリーポイントやターゲットが設定しやすい手法です。三角持ち合いで取引をしたい初心者は、まずは過去のチャートで三角持ち合いを探し出し、デモトレードなどで検証してみましょう。そうすることでダマシへの対処法も分かり、取引の精度も上がります。
三角保ち合いをFXのエントリーに利用すると、以下の2点のメリットも得られます。
特にFX初心者は、チャートの見方がよくわからなかったり、値動きを都合良く解釈したりする傾向があります。しかし、三角持ち合いのチャートパターンは一定であるため、取引するタイミングを狙うことで取引の精度を高め、リスク管理をしやすくするという実践的なメリットがあります。
また、FX初心者は、慣れないうちは根拠に基づかずにエントリーしてしまう傾向もあります。しかし、例えば「三角持ち合いパターン以外は取引しない」というルールを決めておけば、三角持ち合いが出現するまでは取引を待てるようになります。
FXにおいて、待つことはとても重要です。「早く利益を獲得したい」と急いでしまうと正確な読みができなくなり、チャンスを逃したり、思わぬ損失を出したりすることがあります。三角持ち合いが出現した時に取引すると決めておけば、慌てることなく慎重に取引を進められるでしょう。
これらを踏まえた上で、三角持ち合いの以下2つのエントリーポイントを、それぞれ詳しく解説します。
三角持ち合いが発生した時の基本的なトレード方法が、明確にブレイクしたらエントリーすることです。三角形の頂点までは売買エネルギーが蓄積された状態で、どちらかの方向に放出されることで一方向に伸びる動きが出やすいからです。
特に、3種類の三角持ち合いのうち、アセンディング・トライアングル(上昇型)で上方向にブレイクした時と、ディセンディング・トライアングル(下降型)で下方向にブレイクした時は、絶好の狙い目です。どちらもそのままトレンドが継続する確率が高く、利益確定や損切りの計画が立てやすいエントリーポイントになるからです。
価格変動に方向感がなく、横ばいの値動きになっている状況で値幅が極端に収束している時は、絶好のチャンスといえるでしょう。
ブレイク後の値戻りも、絶好のエントリーポイントです。
特に、アセンディング・トライアングル(上昇型)で下方向にブレイクした時や、ディセンディング・トライアングル(下降型)で上方向にブレイクした時など、トレンド継続になるような場面では、戻りを待ってからエントリーすることで、エントリーの精度を高めることができます。
値動きの方向が定まっていないシンメトリカル・トライアングル(均衡型)でブレイクした時も、慎重に戻りを待つ方が反発の弱さを見極めることができ、エントリーの精度が高まるでしょう。
また、三角持ち合いではブレイク直後に「ダマシ」の動きも多く、飛びついてのエントリーは損切りになる場合もあるなど、リスクが高いと言えます。しかし、戻りを待ってからエントリーをすると明確な損切りラインを設定しやすく、リスク管理がしやすくなります。
ただし、戻りを待つ間に価格がそのまま伸びてしまい、チャンスを逃すことがあったり、戻りが深すぎたり、時間がかかりすぎたりすると、ブレイクの勢いがなくなってしまう場合もあるため、ブレイクと戻りの形状を見極める観察力とタイミングのバランス感覚が求められます。

FXにおける利確とは、現在保有しているポジションを決済して利益を確定させることをいい、利確ポイントとは、利確をするのに適切なポイントのことです。
FXでは利益が出ていても、決済をしなければ含み益のままとなり、実際の利益として手元には残りません。含み益が出ているのにもかかわらず、もっと利益を狙おうと保有を続けても、価格が変動して含み益を失ってしまうどころか、含み損に反転してしまうことがあるのです。そのため、利確ポイントを決めることは非常に重要です。
これらを踏まえた上で、ここでは三角持ち合いの利確ポイントを、以下3つのチャートパターンに分けてご紹介します。
それぞれ詳しく説明します。
FXのレンジブレイクは、それまでのレンジ幅と同じ分だけ価格が伸びる傾向があります。レンジブレイクとは、価格がレンジ相場からブレイクし、新しいトレンドが生まれることです。
アセンディング・トライアングル(上昇型)では、このレンジブレイクを三角持ち合いブレイクアップと捉えることで利確ポイントの目安にします。この場合は三角持ち合いの最大幅を求め、レンジブレイク時のレジスタンスラインからの同じ値幅を利確ポイントにします。
当然ながら、相場次第ではさらに上昇することもあります。しかし、逆に利確ポイントに達しないこともあるため、上記はあくまでも目安として覚えておきましょう。
ディセンディング・トライアングル(下降型)の場合も、アセンディング・トライアングル(上昇型)同様、ディセンディング・トライアングルが形成される起点となった価格とその時点のサポートラインの値幅(三角持ち合いの最大幅)と、レンジブレイク時のサポートラインからの同じ値幅まで価格が下落した時点を利確ポイントとします。
シンメトリカル・トライアングル(均衡型)の場合も、先述した方法で利確ポイントを決めます。「三角持ち合いの最大幅」を、ブレイク地点からブレイク方向へ加算するというものです。
ただし、シンメトリカル・トライアングル(均衡型)の場合は、先述の2つの三角持ち合いとは異なり、上下のトレンドラインによって持ち合いが形成されています。そのため、値動きの勢い(モメンタム)やボラティリティが弱い相場では、最大幅まで届かないこともあります。トレンドラインと平行のラインを引き、それを利確ポイントの目安にしたり、最大幅の50~80%あたりに分割して利確ポイントを設定したりするなど、柔軟な対応がよく取られます。

投資の一つであるFXでは、損失を出すことはなるべく避けたいものですが、目先の値動きにとらわれて、損失が出ていても取引をやめられず、どんどん損失が拡大してしまうことは珍しくありません。特に初心者は、損失を取り戻そうと焦って取引を続けて、結果的に大損することもあります。
このような事態を防ぐための手法が、損切りです。
損切りとは、為替相場が予測とは反対の動きをした際に、それ以上損失を出さないよう、損失が出ている状態のポジションを決済することです。これによって、損失を限定的にすることができます。
では、三角持ち合いではどのように損切りすれば良いのでしょうか。
三角持ち合いのダマシとは、予想とは逆の動きをとることです。
多くの場合、ダマシは買い注文と売り注文がせめぎ合い合うことで発生します。一時的に片方の注文が強くなって価格が動いた後、すぐに反対側の注文が多く入って反発するという、その動きがダマシとなってチャート上に現れます。
また、ダマシの多くは「ヒゲ」となって現れます。ヒゲとは、ローソク足の上下から伸びている細い線のことで、最高値または最安値を表しており、始値または終値と高値または安値の差が大きいほど長くなります。そのため、ヒゲが長いと、それだけ多くのトレーダーがダマシに遭遇したと考えられるのです。
ダマシは、レジスタンスラインやサポートラインなどの水平線付近でよく発生します。これらのラインが引かれているポイントでは、多くのトレーダーが同時に意識する価格帯となり、買い注文と売り注文のせめぎ合いが発生しやすくなるからです。
例えば、アセンディング・トライアングル(上昇型)では、レジスタンスラインを上に抜ければ上昇トレンドになるのが一般的です。しかし、三角持ち合いのダマシが発生すると、一旦レジスタンスラインを上に抜けたのにもかかわらず、下落してしまいます。上昇トレンドを予測して買い注文を入れた状態でダマシにあうと、含み損を出してしまうでしょう。
また、ダマシは値動きが細かく時間足が短いほど、頻繁に発生します。5分足でブレイクしても、後から1時間足で見たところ、ただ単にヒゲとなって終わっていたというケースはよくあることです。
したがって、長い時間足で判断した上で、戻りを待つことを意識することも大切です。そうすることで適切な判断ができるでしょう。

FX取引では「相場がどちらに動くのか分からない」というのが通常です。三角持ち合いでもこの状況に違いはないため、特にFX初心者は戸惑う場面が多くあるかもしれません。そのような時に有効な手立てが、OCO注文(オーシーオー注文)です。OCO注文ならリスクを抑えつつ利益を最大限伸ばせます。
OCO注文のOCOとは、一方が他方をキャンセルする意味を表す英語「One Cancels the Other」の頭文字です。その意味通り、OCO注文とは、あらかじめ2つの注文を同時に出しておき、片方の注文が成立した場合、もう片方の注文が自動的にキャンセルされる注文方法です。
例えば、1ドル120円の時に購入し、相場がどちらに動くか分からない状況を想定して考えてみましょう。OCO注文で「1ドル130円になったら利益確定をする」「1ドルが110円になったら損切りをする」という注文を入れ、数日後に1ドル130円になったとします。
すると、「1ドル130円になったら利益確定をする」という注文が実行され、「1ドルが110円になったら損切りをする」という注文は自動的にキャンセルされます。
また、含み損を抱えているポジションを決済しながら損切りができる点も、OCO注文のメリットで、損失を限定しながら取引ができるため、初心者にとっても安心です。
このように、OCO注文は相場の値動きが読めない状況と相性が良いため、リスクを最大限抑えながら三角持ち合いの取引をしたい方にはおすすめの注文方法といえます。
OCO注文を使う際は、ストップ注文の成立と同時にスリッページが発生する可能性があることに注意が必要です。スリッページとは、注文時の価格と決済した価格との間に生じるズレのことです。
スリッページが発生すると、例えば100円で損切りするはずが99円で注文が成立するなど、想定外の損失が出てしまう恐れがあります。特に相場が大きく変動している時はスリッページが発生しやすくなるので注意しましょう。

FXを始めとした投資には「絶対勝てる」という手法や状況はありません。そのため、きれいな形の三角持ち合いが出現したからといって、ダマシに遭わないとも限りません。
ここまで説明しておわかりのように、三角持ち合いのラインの反発は全て同じように動くことはないため、多くのトレーダーがブレイクとダマシを見極めるのに難しさを感じています。
しかし、見極めるポイントは意外にシンプル。三角持ち合いのダマシを見分けるパターンは、主に以下の3つがあります。
それぞれ詳しく説明します。
三角持ち合いでは、反発回数が多いほどラインが機能しているため、ブレイク時の変動も大きくなる傾向があります。サポートラインやレジスタンスラインは、トレーダーが注目する重要な価格帯であり、反発回数が多いほど継続する可能性が高いといえます。
一方、反発回数が少なかったり、ラインがきれいに引けなかったりする場合は、ダマシになりやすいため注意が必要です。少なくとも、3回は反発しているラインをベースに取引を進めましょう。
多くの場合、三角持ち合いのダマシは、ラインをわずかに突破した後に急速に逆戻りします。このラインのズレが典型的なダマシの形です。
価格がラインを一時的に突破しても、本当の転換ではなく一時的な動きである可能性が高いことに注意しましょう。ラインがきれいに揃っていない場合は慎重に取引を行い、エントリーするタイミングを見極めることが重要です。
ダマシは、取引量が少なく相場の安定しない時間帯に多く発生します。そのため、この時間帯で取引する場合はダマシの出現に注意しましょう。
特に、週明けにマーケットがオープンした直後や日付が変わる前後などは、参加しているトレーダーの人数も少ないため、相場が安定しません。チャートもレンジ状態になりやすく、インジケーターもあまり役に立たないため、ダマシに遭遇する可能性が高いでしょう。
三角持ち合いでダマシを避けるためには、三角持ち合いが形成される前に、相場の環境をチェックしておくことが有効です。
例えば、三角持ち合いが出現する前に下降トレンドが発生していれば、三角持ち合いが上方向にブレイクしたらどうなるか、もしくは下方向へブレイクしたらどうなるか、イメージがしやすくなります。このイメージから、「ダマシが出たらこうなる」「このパターンはダマシかもしれない」と、予測できるようになるでしょう。

先述した通り、三角持ち合いが形成されている時は、売り注文と買い注文がせめぎ合っているさなかであり、方向性が定まっていない状態です。そのため、三角持ち合い形成中のエントリーには注意が必要です。
そこでおすすめなのが、インジケーターの併用です。
FXにおけるインジケーターとは、市場状況を視覚的に理解しやすくするためのツールであり、価格や取引量などのデータをもとに計算される数値やグラフのことです。インジケーターを用いて多くの指標を組み合わせて分析すれば、チャートをより正確に把握できるでしょう。
三角持ち合いでおすすめのインジケーターは、以下の2つです。
これらの2つは、どのチャートにも標準で備わっています。難しい設定も必要なく、デフォルトのまま使えるため、初心者でも容易に活用できるでしょう。
ボリンジャーバンドは、中央の移動平均線、上下の標準偏差(σ)から算出した線を組み合わせたテクニカル指標です。売買のタイミングや今後の値動きの予測に役立つため、三角持ち合いとの併用に適しているといわれています。
標準偏差とは、データのばらつき度合いを統計学的に示す値です。ボリンジャーバンドの上下ラインには「±1σ標準偏差」や「±2σ標準偏差」などがあり、以下の確率で過去の為替相場それぞれのライン内に収まると言われています。
上記の線と現在のチャートを見比べることで、現在の価格と過去の価格の差が分かります。価格変動の予測や売買する適切なタイミングを図る時に不可欠な指標になるでしょう。
また、ボリンジャーバンドを見る際は、以下4つのポイントに着目することも大切です。
スクイーズは、ボリンジャーバンドが収縮している状態を指します。この状態では、ボラティリティが低いため、価格が上下するレンジ相場が起こる確率が高くなります。そのため、あまり値動きを期待できる相場とはいえないでしょう。
エクスパンションは、ボリンジャーバンドが拡大している状態です。ボラティリティが高く、どちらか一方向に動くトレンドが発生しやすい状態のため、狙いやすい相場といえるでしょう。
ボージは、エクスパンションによってバンド幅が最も拡大した部分のことです。ボージになるとバンド幅は縮小に向かうため、トレンドが反転する確率が高くなります。また、ポージはトレンドの終了を示唆することが多いともいわれています。
バンドウォークは、価格が1σや2σに沿って一方向に動いている状態です。この状態ではトレンドが継続するため、その方向へより大きく動く確率が高くなります。トレンドが発生している方向へ取引をすれば、大きな値幅を狙えるでしょう。
このように、ボリンジャーバンドは視覚的に分かりやすく、初心者でも容易に利用できる指標です。三角持ち合いが出現した時は活用してみて下さい。
ただし、万能でないことに注意が必要です。ボリンジャーバンドの±2σ標準偏差は約95%と非常に高いですが、裏を返せば5%の確率で外れるということです。数値の高さだけにとらわれて取引をすると、外れた時に損をするかもしれません。このように、例外的な価格変動の可能性を考慮することも大切です。
RSIは「Relative Strength Index」の略で、日本語に訳すと「相対力指数」、つまり買われすぎか売られすぎかを判断するためのテクニカル指標です。RSIは、トレーダーが市場の動向を評価し、エントリーや決済のタイミングを判断するためのツールとしてよく利用されています。
RSIでは、買われすぎか売られすぎかを判断できるため、トレンドの転換ポイントや売買タイミングの見極めに役立ちます。また、短期的な変動を捉えられる指標でもあるため、短時間で取引したい場合にも有用でしょう。
RSIの基本的な使い方は、以下の2つです。
RSIでは、過去一定期間の変動幅における上昇トレンドの値動きの割合が0〜100%の数値でサブチャートに示されます。一般的に、RSIが70%以上なら買われすぎ、30%以下なら売られすぎといわれています。
ダイバージェンスとは、ローソク足とRSIの動きが逆行している状態を指し、トレンドの転換を示すといわれています。例えば、上昇トレンドでダイバージェンスが発生した場合は、下降トレンドへの転換が予想されます。ダイバージェンスが発生したら、トレンドが転換する可能性が高いと覚えておきましょう。
このように、RSIはトレンドの継続や転換ポイントを分析できる便利なテクニカル指標です。相場分析もしやすいことから、初心者にも人気があります。
ただし、単独で使用するのではなく、他のテクニカル指標やチャートパターンと組み合わせて総合的に判断することが重要です。さらに、先述した通り、短期的な変動を捉える指標であるため、長期的なトレンドを判断する場合には不向きといえます。

FXにおける三角持ち合いの主なメリットは、以下の2つです。
FXにおける三角持ち合いのメリットを知れば、今後のトレード戦略やリスク管理、相場動向の予測に役立つでしょう。
それぞれ詳しく解説します。
三角持ち合いを利用することで適切な取引のポイントが分かるため、より根拠に基づいたエントリーができるようになります。勘頼りの取引でリスクをおかすことなく、資金の浪費も防げるでしょう。
先述した通り、人間の思考には多少なりとも偏りがあります。そのため、特に取引に慣れていない初心者は、「ここなら狙える」「まだ上昇するチャンスがある」など、相場の動向を都合よく解釈する傾向があります。
しかし、三角持ち合いは一定の範囲内で相場が変動するため、適切にラインを引くことで偏った主観による判断を防ぐことができます。三角持ち合いを利用して取引を限定すれば、無理な取引で損失を出すリスクも回避できるでしょう。
これまで述べてきた通り、レンジ相場は価格が上昇、また下落する幅が限定されているため、大きな利益を得るのが難しいデメリットがあります。さらに、エントリーポイントも限定されるため、取引の機会が限られてしまう難点もあります。
しかし、三角保ち合いは価格の変動が少しずつ狭くなっていくことで生じ、相場の明確な方向性がないため、レンジ相場であるといえます。つまり、三角持ち合いが出現している状況での取引を避けることで、レンジ相場での取引も避けられるということです。
よって、初心者にとっては、リスクを抑えながら取引できるメリットがあるともいえるでしょう。
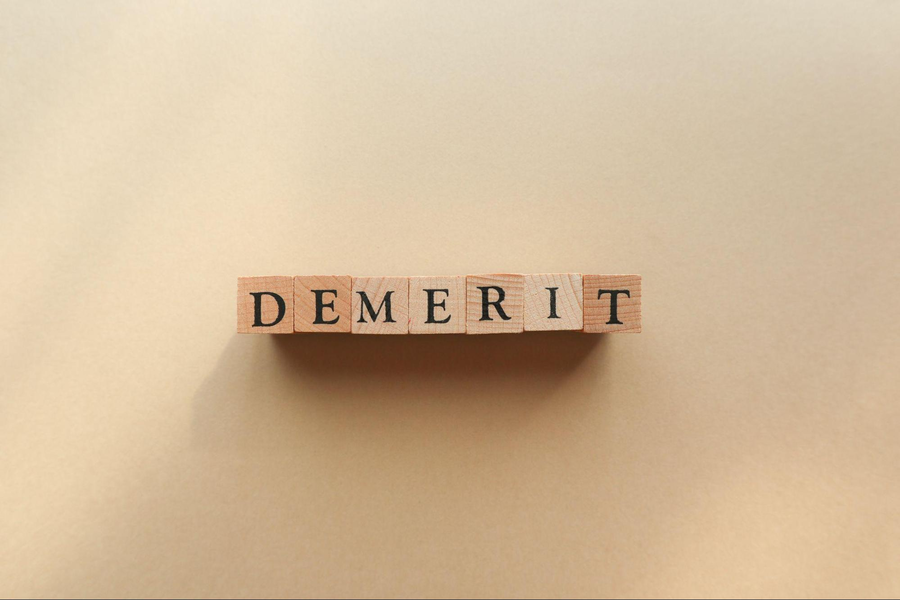
一方、FXにおける三角持ち合いには、以下のデメリットもあります。
それぞれ見ていきましょう。
先述した通り、FXに現れる三角持ち合いはレンジ相場に該当します。
レンジ相場は、一定の変動幅の中で価格がジグザグと上下しているため、三角持ち合いのみで相場の方向性を予想するのは難しいといえます。
そのため、三角持ち合いで取引する際は、上位足などを活用して相場全体の流れを把握したり、三角持ち合いを形成する前の相場状況を分析したりすることが必要です。
これまで説明した通り、三角持ち合いではダマシの発生を完全に避けることはできません。そのため、ダマシへの対策を講じる必要があります。特に、デイトレードやスイングトレードで取引している方は、ブレイクのダマシに遭いやすい傾向があるため注意しましょう。
具体的には、以下のような対策が有効です。
先述した通り、多くの場合、ダマシはエントリー方向に順調に進んでいるように見えた後に逆行して起きます。そのため、エントリーポイントが来た時にエントリーするのではなく、ダマシかどうか確認してからエントリーすることが大切です。ただし、この方法は慣れが必要なので、初心者にはダマシに遭遇したらすぐに損切りすることをおすすめします。
また、複数の時間足でチャートを見て、上位足と下位足の方向性が一致しているか確認することも有効です。例えば、5分足では上昇トレンドに見えても、4時間足の上位足になると下降トレンドに切り替わっているなど、時間足によって相場の方向性が違うことがあるのです。そのため、複数の時間足で相場を分析する癖をつけておくことで、ダマシに遭うリスクを抑えられるでしょう。
相関関係にある通貨ペアの動きを合わせて確認することで、シグナルの信頼性を高めることができます。これは、ダマシを見抜くヒントになるため、特に慎重なエントリーが求められる場面では有効です。たとえば、米ドル/円がレジスタンスラインを上抜けたとしても、同時にユーロ/米ドルが上昇している場合、これはドル売りの動きが強まっていることを示唆しており、米ドル/円のブレイクが"ダマシ"になる可能性があると考えられます。逆に、米ドル/円が上昇し、ユーロ/米ドルが下落しているなら、どちらも"ドル買い"で一致しており、ブレイクが本物である可能性が高まります。
相関分析は、ダウ理論の「複数指数の確認」にも通じる考え方です。ダウ理論には「複数指数の相互確認(複数のチャートが同じ方向に動くことでトレンドを確認する)」という考え方があります。これは、一つのチャートだけでは判断を急がず、別の指標・市場・通貨でもトレンドが確認できるかをチェックするというものです。
FXではこれを「相関する通貨ペアを通じて確認する」という形で応用できます。
三角持ち合いは、相場が荒れていると機能しないことがあります。上方向にブレイクしたのに下降トレンドが始まったり、三角形の中からたびたび飛び出したりと、非常に読みづらくなってしまうため、初心者は判断に迷う場面が多くなるでしょう。
特に、スキャルピングで取引している方にとっては、勝率が悪くなってしまうことがあります。経済指標や国際情勢、要人発言など為替相場に影響を与えるようなイベント前後は、取引を控えることが賢明です。
ここで、三角持ち合いの特性上、「両建て」をするのは有効なのではと思う方もいるかもしれません。FXにおける両建てとは、同一通貨の買いポジションと売りポジションの両方を同時に保有することをいいます。しかし、三角持ち合いでの両建ては非常にリスクが高くなるため注意が必要です。
理論上では、三角持ち合い中に両建てをしておけば、反対の方向にブレイクした注文だけを損切りして、ブレイクした方向の注文だけを保有すれば利益を確保できることになります。
しかし、前述した通り、三角持ち合いではダマシの出現を避けられないことから、ブレイクしたからといってその方向にトレンドが形成されるわけではありません。両建てがうまくいけば利益を伸ばせますが、反対にどちらのポジションも負ければ、その分損失も拡大してしまいます。

FXにおける三角持ち合いはチャート分析の一種で、価格が一定の範囲内で推移しながら、徐々に変動幅が狭くなっていくことで三角形を形成するパターンを指します。
三角持ち合いには、以下3つの種類があります。
FX初心者が三角持ち合いを活用する際のポイントは、きれいな三角形のチャートを選ぶことと、長い時間足の三角持ち合いを優先することです。きれいな三角形は多くのトレーダーに認識されやすく、大きなブレイクが期待できるため、初心者も読みやすいチャートです。逆に形が崩れているとトレーダーの判断が分かれ、チャートの動きが不規則になって失敗のリスクが高まるため、注意が必要です。
三角持ち合い発生中は、大きな利益を得られるチャンスがあるといわれています。しかし、三角持ち合いだけでは、相場の方向が分からず、ダマシも完全には避けられません。さらに、相場が荒れている時は機能しないこともあるため、特にFX初心者は判断に迷う場面が多くなるでしょう。
そのため、今回紹介した損切り・利確のポイントを見極めながら、3つのチャートパターンの分析方法などをうまく活用することが大切です。
これからFXを始める方は、まず短期的な少額取引から始めて、三角持ち合いを活用した取引に慣れていきましょう。
SBI FXトレードは業界トップクラスとなる「34種類」の通貨ペアがあり、1通貨単位から取引できるため、非常に少ない資金からFX取引が可能です。
また、スプレッドは業界最狭水準となっており、利益を上げやすい環境が整っているため、初心者の方にも安心してご利用いただけます。
まずはSBI FXトレードで口座を開設し、FX取引を始めてみましょう。
SBI FXTRADE
FX(外国為替証拠金取引)は異なる通貨を売買し、売買時のレートによって生じた差額で利益を出そうとする取引です。
SBI FXTRADEは、スプレッドやスワップポイント、通貨ペア数など、業界最良水準のサービスをご提供しています。また、初心者の方から、上級者までご満足いただける取引ツールをご用意しております。
この記事を監修した人
SBIリクイディティ・マーケット株式会社
金融市場調査部長
上田眞理人