UPDATE 2025.03.07
POST 2025.03.07
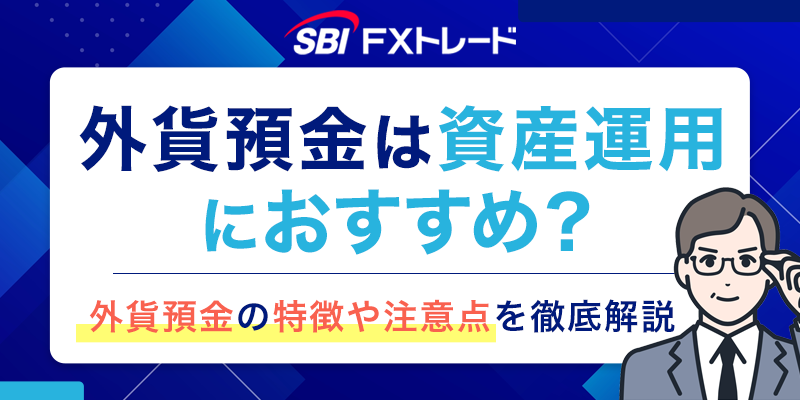
「外貨預金」と聞くと、難しそうなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?しかし、外貨預金は口座を開設すれば少額から取引が可能であり、為替変動の仕組みなども学びやすく、初心者にもおすすめの資産運用です。
外貨預金についてしっかり理解すれば、資産運用の選択肢が広がるでしょう。本記事では、外貨預金の概要やメリット・デメリットなどをご紹介します。また、記事の後半では外貨預金を始める上での注意点も解説します。外貨預金での資産運用を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

外貨預金とは、日本円を米ドルやユーロなどの外貨(海外の通貨)に換えて預金することを指します。銀行などの金融機関で専用の口座を開設すれば、すぐに外貨預金を開始できます。
日本では、1993年頃から現在に至るまで低金利が続いており、銀行預金による利息の恩恵を感じづらい環境が続いています。それに対して、海外には日本よりも高金利の国がいくつもあり、それらの国の通貨で預金をすれば、日本円で預金しているよりも受け取れる利息が多くなります。
例えば、米ドルはアメリカの通貨ですが、アメリカの金利はおおよそ年4%前半となっています。それに対して、日本の金利は0.5%(2025年2月5日現在)であるため、日本円で預金しているよりも、日本円を米ドルに換えて預金した方が、より多くの利息を受け取れます。
このように、日本と海外の金利差によってより多くの利息を受け取ることを目指すのが外貨預金の一般的な運用方法です。
外貨預金といっても、以下のようにさまざまな種類があります。
それぞれ金利や特徴が異なるため、運用目的に合わせて適切な外貨預金を選びましょう。
外貨普通預金は、日本円の普通預金と同じように、日本円以外の通貨(外貨)で預け入れや引き出しができる預金です。外貨の方が日本円よりも金利が高いケースが多く、利息の受け取りを期待できます。
外貨定期預金は、一定期間(1ヶ月、3ヶ月、1年など)外貨を預けて、利息を得る預金です。通常、外貨普通預金よりも高い利率が設定されていますが、原則として満期日まで引き出せず、期間中の中途解約にはペナルティが発生するケースもあります。
外貨貯蓄預金は、預け入れ金額に応じて段階的に利率が上がる外貨預金です。1ヶ月ほどの一定期間が過ぎたあとは自由に入出金が可能という特徴を持ち、金利は外貨普通預金より高く、外貨定期預金より使い勝手の良さがあります。貯蓄や短期的な運用に向いています。
外貨通知預金は、一定の通知期間(通常2日〜1週間)を経て引き出しが可能な預金です。普通預金より高い利率が提供されますが、引き出しまでに時間がかかるため、資金の流動性がやや制限されます。
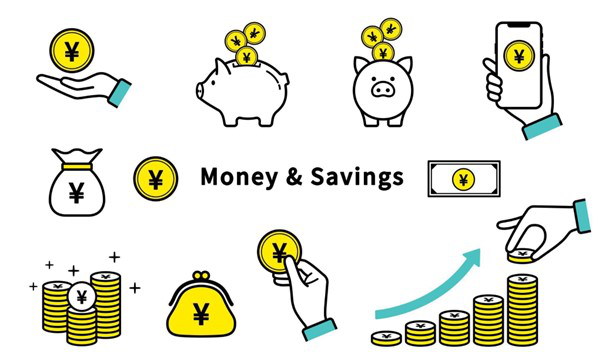
外貨預金のメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。
それぞれ順番に解説します。
外貨預金の大きなメリットの一つは、通常、日本円の預金よりも高い金利が適用される点です。
特に、経済が成長している国やインフレ率が高い国の通貨では、日本の低金利と比較して、預金金利が高く設定されています。例えば、日本と他の国の金利は、以下のように差があります。
【2025年2月5日時点の各国の政策金利】
| 国名(通貨) | 金利 | 100万円を一年間預けた場合に受け取れる利息 |
|---|---|---|
| 日本(日本円) | 0.5% | 5,000円 |
| アメリカ(米ドル) | 4.25〜4.50% | 4万2,500円〜4万5,000円 |
| トルコ(トルコリラ) | 45.00% | 45万円 |
このように、同じ資金を預ける場合でも、日本円の預金より多くの利息を受け取ることができます。ただし、預け入れる銀行によって金利が異なるので注意してください。
外貨預金のメリットとして、円安となった際に為替差益を得られる可能性がある点が挙げられます。
日本円から外貨に換えて預金し、その後に円安が進むと、日本円に戻す際に為替差益が発生します。例えば、1ドル=150円の時に預金し、その後1ドル=160円になった場合、同じ1ドルでも日本円に戻す際に10円の利益が出ます。これは外貨預金ならではの特徴で、円安局面で利益を得ることができます。
2025年に入っても、円安が続いています。仮に、3年前に100万円を米ドルで預けていたら、円安の影響により単純計算で50万円ほどの為替差益が生じています。価格の動向をしっかりと確認し、適切なタイミングで取引すれば、円安の恩恵を最大限に活用できます。
外貨預金は、初心者でも比較的始めやすい資産運用であるといえます。
株式や不動産などの他の資産運用と比較すると、外貨預金はシンプルで分かりやすい仕組みとなります。銀行口座を持っていれば手軽に外貨預金を始められるため、始めるにあたって大きな資産や複雑な手続きは必要ありません。
また、外貨預金は変動要因が基本的に為替相場のみであるため、ドル建ての株式などと比較すると変動が緩やかだと言えます。さらに、預金に対しては金利がつくため、為替変動がないと仮定すれば資金は単純に増えていきます。
それに対して、米国株式などは、為替相場に加えて株価も変動するため振り幅が大きく、場合によっては資産が半分以下になる恐れもあります。
以上のような理由から、外貨預金は初心者でもリスクを抑えて始めやすい資産運用といえるでしょう。ただし、どの外貨も国の政策や経済状況によって金利が変動するため、長期にわたって金利による利益が保証されているわけではない点には注意してください。

外貨預金で資産運用するデメリットは、以下の3つが挙げられます。
どれも初心者が理解しておくべき内容なので、分かりやすくご紹介します。
外貨預金のデメリットの一つは、円高が進行した場合に為替差損が発生するリスクがある点です。
外貨預金は、日本円を外貨に換えて預けることで運用されますが、預金期間中に円高が進むと、日本円に戻す際に外貨の価値が下がり、結果として元本割れが生じる可能性があります。
例えば、1ドル=160円の時に100万円分をドルで預金し、その後1ドル=150円まで円高が進んだ場合は、単純計算で6万円程度の損失が発生します。例えば、160円の時に5,000ドル預金し、150円まで円高が進んだら、5万円の損失となります。短期的な為替変動が大きい市場では、このリスクが顕著になるため、為替相場の変動に注意する必要があります。
外貨預金を行う際には、為替変動リスクを十分に理解し、円高に備えたリスク管理の戦略を立てることが重要です。
外貨預金を行う際に、為替手数料がかかる点もデメリットの一つです。
為替手数料とは、日本円を外貨に換える際および外貨を日本円に戻す際に発生する費用で、通常は100円当たり1〜5円ほどの手数料がかかります。為替手数料は買う際と売る際の両方で発生するため、頻繁に売買を行う場合は、特に利益を圧迫する要因となります。
このため、外貨預金を始める前に、手数料の詳細を確認し、取引コストを最小限に抑えるための工夫が求められます。長期保有を行い頻繁な売買を避けることで、手数料の負担を軽減することが可能です。
外貨預金は、預金保険制度の対象外である点も重要なデメリットです。日本の銀行預金には、銀行自体が経営破綻に陥ったとしても元本1,000万円までが保護される「預金保険制度」がありますが、外貨預金はこの保護の対象外となっています。
つまり、外貨として預け入れた銀行が破綻した場合、外貨預金はそのまま返還されず、預金者は一部または全額を失うリスクがあります。
外貨預金を行う際は、預け入れる銀行の財務状況や信用力を確認し、リスク分散のために複数の銀行や通貨に分散して預金するのも有効な対策となります。

外貨預金は、日本円を外貨に換えるという点でFXとよく混同されがちです。ここでは、外貨預金とFXの3つの相違点について分かりやすく解説します。
レバレッジとは、証拠金を預けることで、自己資金の何倍もの取引を行える仕組みを指します。FXでは、レバレッジを利用することで、実際に預けた資金の数倍から数十倍の取引が可能です。その一方で、外貨預金はFXとは異なりレバレッジが利かないため、預けた金額そのものが運用の対象となります。
これにより、FXは少ない元手で大きな利益を狙えますが、同時に損失も拡大するリスクがあります。外貨預金は少額の資金で大きな利益を得ることは難しいですが、損失のリスクも限定的で、リスク管理が比較的容易といえるでしょう。
外貨預金は、FXに比べて頻繁に売買する必要がありません。
FXは、相場の変動を利用して頻繁に売買を繰り返すことで利益を追求することが多いため、常に市場を監視し、タイミングを見極める必要があります。それに対し、外貨預金は一定期間そのまま保有して、金利や為替差益を得ることが一般的です。
以上のような理由から、外貨預金は長期的な運用に向いており、手間をかけずに資産運用ができます。
外貨預金は、日本円を米ドルなどの外貨に換えて保有するという性質上、円安になれば利益になり、円高となれば損失になります。
一方で、FXは主に短期的な相場の変動を利用して利益を追求するため、円安でも円高でも利益を得るチャンスがあると同時に、損失を抱えるリスクがあります。

外貨預金の対象となる各国の通貨は、種類が多くどれを選ぶか悩む方も多いでしょう。ここでは、各国の通貨について、それぞれの特徴を簡単にご紹介します。
米ドル(USD)は、世界の基軸通貨です。世界で最も取引される通貨であり、貿易の決済や投資に多く使われています。雇用統計やGDP、インフレ率など米国の重要な経済指標に影響されやすい点や、さまざまなメディアで為替相場や動向が報道されるなどの理由から、比較的値動きを把握しやすいのが特徴です。
ユーロ(EUR)は、欧州連合の主要通貨であり、米ドルに次いで取引が多い通貨です。ユーロ圏の経済規模の大きさと安定性から、通貨としての信頼性が米ドルの次に高いといえるでしょう。欧州中央銀行の経済政策や、ユーロ圏の中で最大の経済規模を誇るドイツの経済指標が、ユーロの値動きに大きく影響します。
ポンド(GBP)は、比較的安定した外貨であり、特に長期的な資産保全を目指す方に適しています。イギリスの経済や金融システムが強固であるため、信用度は高いですが、米ドルやユーロと比較すると取引が少なく、値動きが大きいのが特徴です。
豪ドル(AUD)は、オーストラリアが鉄鉱石をはじめとした豊富な鉱物資源に恵まれていることから、資源国通貨の代表格とされています。資源価格の動向に大きく影響される他、オーストラリアと取引の多い中国の経済情勢によって価格が変動します。
スイスフラン(CHF)は、世界的に「安全通貨」として認識されています。スイスが永世中立国であるという政治的安定性と経済の強固さが背景にあり、リスクを避けたい方に人気です。金利は非常に低いですが、リスク回避の手段としては優れています。また、EU諸国と強い貿易関係にあるため、ユーロの値動きに影響を受けやすい傾向があります。
メキシコペソ(MXN)は、高金利であり、短期的な利回りを狙う方に人気があります。ただし、メキシコの経済は米国や石油価格の影響度が高いため、これらの要因による価格変動が激しく、リスクが高い点に注意が必要です。
トルコリラ(TRY)は非常に高い金利が魅力ですが、通貨の急激な価値変動がリスクとして挙げられます。トルコの政治的・経済的不安定さがトルコリラの変動を引き起こすため、大きなリターンと同時に大きなリスクを抱えることになります。
南アフリカランド(ZAR)は、資源国通貨であり、特に金やプラチナの価格動向に影響を受けます。高金利が魅力ですが、政治的リスクや経済不安、通貨の流動性の低さから、リスクが高いとされています。南アフリカランドで外貨預金をする場合は、資源価格や国内政治の動向に注意が必要です。

外貨預金は、FXや株式と比較すると仕組みとして単純であり、リスクを抑えての運用が可能です。とはいえ、まったくのノーリスクということはありません。
これから外貨預金を始めようと検討している方は、以下の2点について注意してください。
外貨預金を始める際は、「為替リスク」に注意する必要があります。為替リスクとは、預金した外貨の価値が、価格の変動によって変わるリスクを指します。
例えば、100万円を米ドルに換えて預けた際に、米ドル/円が150円から120円に動いた場合は、単純計算で20万円ほどの為替差損が生じてしまいます。
逆に、価格が円安に進めば利益が出ますが、為替相場の変動は予測が難しいため、一定のリスクがあるとして考えるべきでしょう。
預金額が大きければ大きいほど、損失額も大きくなるため、初めての外貨預金で不安な方は、少額から始められるSBI FXトレードの「つみたて外貨」がおすすめです。
外貨預金は、短期的な利益を狙うのではなく、長期的な視点での運用を意識しましょう。短期間で日本円に戻してしまうと、為替手数料が高くなり、資産運用としては非効率です。
具体的には、日本円を米ドルなどの外貨に換える際と、外貨を日本円に戻す際のそれぞれに手数料がかかります。そのため、短期間に何度も売買を繰り返すと、その分手数料負担が大きくなってしまいます。
さらに、短期間の外貨預金だと為替変動の影響を受けやすく、安定した資産運用は難しいといえます。「つみたて外貨」のように、毎月一定額を積み立てて長期間の運用をすることで為替変動のリスクを最小限に抑えられるという点を覚えておきましょう。

本記事では、外貨預金の仕組みやメリット・デメリットなどについて詳しくご紹介しました。
外貨預金は、FXや株式と比較すると初心者が取り組みやすい一方で、預金保険対象にならないなどのデメリットも存在します。また、円高が進んだ場合は元本割れのリスクもあるため、外貨預金の仕組みや各通貨の特性を理解しつつ、余剰資産の中で運用するのがおすすめです。
SBI FXトレードの「つみたて外貨」では、為替変動などのリスクを最小限に抑えながら、長期の外貨運用がスタートできます。
外貨預金より柔軟に売買したいけれど、普通のFX投資はリスクが高いと感じる方は、SBI FXトレードの「つみたて外貨」で外貨投資を始めてみましょう。
無料で口座開設ができるので、外貨運用に興味がある方はぜひご利用ください。
SBI FXTRADE
FX(外国為替証拠金取引)は異なる通貨を売買し、売買時のレートによって生じた差額で利益を出そうとする取引です。
SBI FXTRADEは、スプレッドやスワップポイント、通貨ペア数など、業界最良水準のサービスをご提供しています。また、初心者の方から、上級者までご満足いただける取引ツールをご用意しております。
この記事を監修した人
SBIリクイディティ・マーケット株式会社
金融市場調査部長
上田眞理人